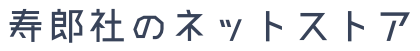-


近現代アイヌ文学史論⸺アイヌ民族による日本語文学の軌跡〈現代編〉
¥3,190
絶えまない逆境を乗り越えて、発展を遂げてきた現代アイヌ文学。その戦後から今日までの軌跡に光を当てる。 小説、評論、エッセイ、詩歌、自伝、新聞、雑誌、同人誌⸺〈近代編〉と併せて1000頁を超える在野研究の金字塔、完結。 須田茂 著 2025年9月刊 四六判/並製/564頁 本体2900円+税〔税込3190円〕 ISBN 978-4-909281-68-5 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第1章 戦後のアイヌ文学の幕開け⸺言論活動の復活 一節 高橋真と『アイヌ新聞』の挑戦 二節 『北の光』と新生北海道アイヌ協会 三節 進駐軍とアイヌ民族の言論活動 第2章 知里真志保の業績と影響 一節 知里真志保の「アイヌ系日本人」論 二節 アイヌの人たちの知里真志保像 三節 知里真志保と近現代アイヌ文学 四節 現代アイヌ文学への貢献 第3章 現代小説の台頭 一節 鳩沢佐美夫(1935〜1971) 二節 上西晴治(1925〜2009) 三節 鳩沢佐美夫と上西晴治の交錯 第4章 1970年代のアイヌ文学の展開 一節 「対談 アイヌ」以後の『日高文芸』 二節 「葦の会」と『葦の会だより』 三節 新聞『アヌタリアイヌ⸺われら人間』 四節 佐々木昌雄の仕事 五節 1970年代のアイヌ著述家群像 六節 同人誌『北方群』 第5章 脱植民地化への挑戦 一節 結城庄司(1938〜1983) 二節 荒井源次郎(1900〜1991) 三節 海馬沢博(1919〜1987) 第6章 「エカシ」たちの復活とその仕事 一節 森竹竹市・貫塩喜蔵の復活 二節 山本多助(1904〜1993) 三節 貝澤正(1912〜1992) 四節 葛野辰次郎(1910〜2002) 第7章 337 萱野茂の仕事 第8章 351 アイヌ民族による現代詩歌 一節 現代詩 二節 短歌 三節 俳句 第9章 多様化する現代アイヌ文学 一節 自伝文学の活性化 二節 児童文学の広がり⸺絵本と童話 三節 1980年代以降の主なアイヌ文学の著作 第10章 現代アイヌ文学についての試論 一節 現代アイヌ文学とは何か 二節 現代アイヌ文学の潮流 三節 世界の先住民族文学との比較 四節 アイヌ文学の展望 あとがき 主な参考文献 近現代アイヌ文学史年表(1866〜2022) 文献索引 人名索引 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 須田茂(すだ・しげる) 1958年東京都生まれ。学習院大学法学部政治学科卒。民間企業に勤務する傍ら明治以来の近現代のアイヌ文学を研究。著書に『近現代アイヌ文学史論⸺アイヌ民族による日本語文学の軌跡〈近代編〉』、共著に『札幌地方同人雑誌作品選集 第1集』『北海道同人雑誌作品選集 第2集』がある。北海道文化財保護協会会員。神奈川県川崎市麻生区在住。
MORE -

北海道大学もうひとつのキャンパスマップ——隠された風景を見る、消された声を聞く
¥1,760
※ポプラ並木やクラーク博士は載ってません アイヌコタン、植民地主義、軍事研究…… 札幌のド真ん中に位置する“観光名所”北海道大学札幌キャンパスには、大学が積極的に語ろうとしない〈歴史〉がある—— 有志教員と学生が外部の研究者にも協力を仰いで完成させた、北大の知られざるもうひとつの歴史ガイド。 「開拓150年」「ウポポイ開設」「オリンピック招致」に湧く今こそ身につけておきたい、これからの北海道を考えるうえで重要な視点の詰まった一冊。 北大ACMプロジェクト 編 2019年6月刊[初版] 2024年6月刊[第2版] 四六判/並製/208頁 本体1600円+税〔税込1760円〕 ISBN 978-4-909281-15-9 C0026 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 [I かつての風景を想像してみる] あるアイヌ遺骨のふるさと⋯⋯小田博志 コトニ・コタンと琴似又市氏⋯⋯谷本晃久 恵迪寮の地下に眠る農耕集落⋯⋯高瀬克範 植物園の竪穴住居跡⋯⋯高瀬克範 アイヌ音楽に影響を受けた伊福部昭⋯⋯前川公美夫 [II 北大の植民地主義を考える] 1015人が眠るアイヌ納骨堂⋯⋯植木哲也 佐藤昌介の植民学講座⋯⋯番匠健一 林善茂によるアイヌ差別講義事件⋯⋯植木哲也 「国際社会」における新渡戸稲造⋯⋯小山田伸明 新渡戸稲造と植民地台湾の農民⋯⋯張易臻 古河講堂と足尾銅山鉱毒事件⋯⋯小田博志 古河講堂「旧標本庫」人骨放置事件⋯⋯井上勝生 開拓使仮学校と東京イチャルパ⋯⋯関口由彦 [III 北大と戦争の関わりを知る] 大本営門標と行在所門標⋯⋯阿知良洋平 スパイに仕立て上げられた北大生と英語教師⋯⋯立木ちはや 北大工学部の軍事研究⋯⋯山形定 軍事研究に関する議論を巻き起こした中谷宇吉郎⋯⋯笹岡正俊 憲法裁判と学生に向き合った深瀬忠一⋯⋯前田輪音 [Ⅳ 大学と学問のあり方を問う] 森林科初代教授・新島善直の足跡⋯⋯小池孝良 演研青テント撤去事件——大学の土地・施設利用をめぐる闘い⋯⋯桃井希生 北大初の女子トイレの設置を求めて⋯⋯下郷沙季 大学を開く——アイヌ学/和人学をめざして⋯⋯モコットゥナㇱ 先住民と大学の関係を考える——カナダの事例から⋯⋯近藤祉秋 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【編者略歴】 北大ACMプロジェクト 北海道大学の埋もれた歴史を掘り起こし、ACM(オルタナティブ・キャンパス・マップ)を制作するために集まった北大の有志教員と学生のグループ。
MORE -

海のアイヌの丸木舟——ラポロアイヌネイションの闘い
¥2,640
アイヌにとって川で捕るサケは、神の魚(カムイチェプ)であり主食(シエペ=本当の食べ物)であった。その川サケ漁を明治政府は一方的に禁じ、今日に至っている。先住権としての川サケ漁の権限を求めて丸木舟を作り、明治以来の日本の不正義に立ち向かうアイヌ民族団体の激動の日々と、先住権問題の核心を追った渾身のルポルタージュ! 青柳絵梨子 著 2023年6月刊 四六判/並製/360頁 本体2400円+税〔税込2640円〕 ISBN 978-4-909281-53-1 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに プロローグ 丸木舟の出航 丸木舟での川サケ漁/新しいサケを迎える儀式/伝統舞踊 ラポロアイヌネイションとは 第一章 カムイチェプ 1 丸木舟を作る 送り出しのカムイノミ/丸木を浮かべる/受け取りのカムイノミ/丸木舟作りと川サケ漁の復活/記紀に登場する「まつろわぬひとども」「蝦夷」/アイヌの信仰/アイヌとサケ資源/北海道旧土人保護法の制定/アイヌの人口調査/浦幌アイヌ協会の設立 2 米国のサーモンピープルから学ぶ 「あなたの物語を伝えなさい」/フィッシュウォーズの勃発/先住民は環境保護運動のリーダー/漁師の誇り/ダムを撤去させた一〇〇年の闘い/ダム撤去による生活の変化 3 コタンの再生に向けて 先住権の持ち主/複数形になっている権利行使の主体/サケ捕獲権確認訴訟のための勉強会/二風谷ダム訴訟/たった二人の反乱/文化享有権とは何か/国の反論/二風谷ダム訴訟の判決/司法が認めた「アイヌは先住民族」 第二章 ウポポイ vs 丸木舟 1 アイヌ新法が成立するまで 北海道ウタリ協会の陳情/「アイヌ民族に関する法律(案)」/紛糾した北海道アイヌ協会の再建総会/「アイヌ協会」から「ウタリ協会」への名称変更/法案作成のきっかけ/七〇年代前半の「ウタリ対策事業」構想/新法制定の検討と法案作成の動機/一九八四年「ウタリ問題懇話会」発足 2 先住権外し 舟にコタンコロカムイを描く/長根弘喜の意気込み/舟のひび割れ/サケ定置網漁の準備/「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」/二〇〇八年「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」設置/遺骨のDNA研究/土地・資源の「返還等ではなくて」/アイヌ施策推進法へ/ウポポイ構想の出現 3 ウポポイの開業と丸木舟の完成 ウポポイへ行ってみる/文様の揺らぎ/「仮に悲しい歴史があるとすれば」——文科相の発言/二〇二〇年七月、ウポポイ開業/「丸木舟、完成です!」/チプサンケ/丸木舟の着水/ラポロアイヌネイション誕生/ほんとにラポロでいいの? 第三章 墓標 1 アイヌ遺骨発掘の歴史 英国領事館員による幕末のアイヌ遺骨盗掘/外交問題に発展した遺骨盗掘事件/小金井良精の北海道発掘旅行/日本学術振興会の第八小委員会/児玉作左衛門の大量発掘/幕末に盗掘された遺骨を再び掘り出す/児玉作左衛門の「研究成果」/戦後も発掘を続ける/児玉コレクション 2 コタンへの返還と新たな問題の発生 再埋葬のカムイノミ/浦幌町の共同墓地への再埋葬/イチャルパ——先祖供養の儀式/闘いの始まり——海馬沢博の北大への質問状/北大の対応——ウタリ協会に限定して/「標本保存庫」としてのアイヌ納骨堂の完成/人骨台帳をめぐる小川隆吉の闘い/北大開示文書研究会の側面支援/小川・城野口らの提訴/小川・城野口に続く人々/北大との和解と「コタンの会」結成/白老の慰霊施設への遺骨集約は許さない 3 先住権の行使 遺骨返還を糸口に/浦幌アイヌ協会の意識の変化/丸木舟で初めてのサケを捕る/念願のアシリチェプノミ/サケの定置網漁/丸木舟作りという山を越えて/日本とアイヌのいびつな関係を正すラストチャンス エピローグ 新しい社会をめざして 「アイヌの美しき手仕事」展/伝統的サケ漁と訴訟のその後 関連年表 あとがき 参考文献・資料 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 青柳絵梨子(あおやぎ・えりこ) 1984年東京生まれ。大学卒業後、共同通信社に入社。大阪支社社会部、さいたま支局、東京エンタメ取材チームなどを経て、2013-2015年釧路支局、2015-2020年札幌支社に勤務(うち2年間休職してモスクワへ)。著書に、東京エンタメ取材チーム時代の新聞連載をまとめた『〈ルポ〉かわいい!——竹久夢二からキティちゃんまで』(寿郎社)がある。
MORE -

アイヌモシリ【静かな大地=北海道】に生きて——昭和十年、日高地方に生まれたある高校英語教師の自叙伝
¥2,860
〈屯田兵〉の孫として生まれ、多くのアイヌの人々が暮らす村で育ち、やがて「アイヌ共有財産裁判」の支援など、アイヌ民族の権利回復運動に全身全霊で取り組んだある元高校英語教師の「昭和(戦前・戦後)」「平成」「令和」の記録。 2021年9月刊 A5判/並製/528頁+口絵12頁 本体2600円+税〔税込2860円〕 ISBN 978-4-909281-38-8 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 第1章 北海道と家族の歴史 1 アイヌ文化は残っていた 2 北海道は日本の「内国植民地」であった 3 私の祖父は屯田兵家族として北海道へ来た 第2章 幼児期から大学卒業まで 1 動物をたくさん飼う生活 2 「新冠御料牧場」のど真ん中、戦争に負けてどうなったか 3 転校して浦河高校へ 4 大学時代 第3章 教員生活 1 伸び伸びと教育活動ができた 2 新年度が始まってから、急遽の依頼で母校・浦河高校へ 3 教育の総仕上げとなった苫小牧東高校 4 札幌東商業高等学校 第4章 定年後の旅の記録 1 地球一周ピースボートの旅〈1〉 2 地球一周ピースボートの旅〈2〉 3 地球一周ピースボートの旅〈3〉 4 古道・様似山道を歩く 5 芭蕉「おくのほそ道」を辿る旅 6 知床世界遺産を歩く八〇代の三人旅 第5章 教育外の組織的活動(サークル活動) 1 札幌浦高会(同窓会) 2 NMFスキークラブ 3 ソーシャル・ダンス 4 プロジェクト・ウエペケレ 5 ピアニヤン 6 北海道を歩こう 第6章 「少数民族問題懇談会」とその他のアイヌ民族の課題 1 少数民族問題懇談会、旗揚げ 2 先住民族問題と教育 3 アイヌ民族に関する法律(案) 4 「アイヌ民族に関する法律」(アイヌ新法)に関する要望書 5 アイヌ民族の復権運動と差別表現を考える 6 アイヌ民族の歴史と実態を東北に求めて 7 外部講師の依頼で、アイヌ民族を語った 8 作文「差別」 竹内公久枝 第7章 「アイヌ民族共有財産裁判」 1 共有財産返還問題の本質と経過 2 アイヌ民族共有財産の発生と歴史的経過 3 地裁・高裁での取り組みと判決の特徴、課題は何か 第8章 身辺雑記 1 自宅の新築について 2 野菜・果樹を育てて 3 スクラップブック 第9章 英語の教育実践 1 3分間スピーチの実践 2 高校1年で、何をどう教えているか 3 竹内公久枝さんの作文「差別」を英文にして 4 戦争体験の聞き取り調査を英文にして 5 北海道での人権教育 6 アンネ・フランクの実践 7 英語スピーチコンテスト —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 大脇徳芳(おおわき・のりよし) 1935年(昭和10年)、北海道沙流郡平取村に生まれる。 新冠村・元神部小学校、新冠小学校をへて新冠中学校卒業。 静内町・静内高校をへて浦河町・浦河高校卒業。 1955年、北海道学芸大学函館分校1類中学コース文科入学。 1957年、北海道学芸大学札幌分校1類中学コース文科(英語科)転入。1959年卒業。 様似中学校、浦河高校、苫小牧東高校、札幌東商業高校の英語科教師を務め、1996年、定年退職。その間、「少数民族問題懇談会」を立ち上げ、会長としてアイヌ民族の権利回復運動や「アイヌ共有財産裁判」の支援活動などに携わる。 現在、「少数民族懇談会」顧問、「札幌浦高会」顧問、「プロジェクト・ウエペケレ」メンバー。著書に『ポロ リムセ——少数民族懇談会23年の歩み』(アイワード)。
MORE -

アイヌの法的地位と国の不正義——遺骨返還問題と〈アメリカインディアン法〉から考える〈アイヌ先住権〉
¥2,310
〈アイヌ遺骨返還訴訟〉の弁護人である著者が、近世以降のアイヌと日本国の関係を問い直し、アメリカで19世紀前半に確立した〈インディアン法〉と比較しながら〈アイヌ先住権〉の確立を訴えた、初の法学的アイヌ研究の書。 市川守弘 著 2019年4月刊 四六判/並製/232頁 本体2100円+税〔税込2310円〕 ISBN 978-4-909281-14-2 C0032 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はしがき 序章 アイヌ遺骨の返還から〈アイヌ法〉の確立へ 一、研究目的でのアイヌ遺骨の収集 二、江戸時代のイギリス人によるアイヌ遺骨発掘事件 三、遺骨返還拒否の理由は何か 四、遺骨返還訴訟の提起と北海道大学の主張 五、日本政府の遺骨返還についての基本的考え 六、アイヌの人たちの主張 七、裁判所による和解勧告とその影響 八、アイヌ集団(コタン)の権限 第一章 先住民族の権利に関する国際連合宣言 一、先住民族の権利に関する国際連合宣言 二、国際条約と国内法の整備 三、勝利は勝ち取るもの 四、日本国政府の義務 第二章 歴史から見たアイヌの法的地位 一、アイヌはどのように見られてきたか 二、江戸時代におけるアイヌ法的立場 第三章 明治政府によるコタンへの侵略 一、国際法を無視した明治政府 二、明治政府の新しい法制度(自然資源) 三、生活・文化面での明治政府の新しい法制度 四、新しい法制度の結果 第四章 〈アメリカインディアン法〉から学ぶこと 一、〈アメリカインディアン法〉とは何か 二、アメリカにおける先住権とその主体 三、アメリカ合衆国とインディアンの歴史 四、アメリカにおけるインディアンの同化政策 五、インディアントライブは主権を有する集団 六、主権とは何か 七、領土の線引きと先住民との関係 八、先住権と条約——サケ捕獲権をめ巡って 九、アイヌの先住権とインディアン法との比較 第五章 憲法と先住権、先住権の主体としてのコタン 一、憲法と先住権 二、コタンは存在するのか——現代におけるコタンの考え方 第六章 北海道旧土人保護法の廃止と日本国の向かう先 一、北海道旧土人保護法について 二、北海道旧土人保護法とドーズ法の異同 三、文化振興法とは何であったのか 四、日本の向かう先 おわりに 参考文献 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 市川守弘(いちかわ・もりひろ) 1954年東京生まれ。中央大学法学部卒。弁護士(1988年弁護士登録、現在旭川弁護士会所属)。1999~2002年、コロラド大学ロースクール自然資源法センターに留学。著書に『アメリカインディアン法の生成と発展——アイヌ法確立の視座として』(日弁研修叢書)、共著書に『アイヌの遺骨はコタンの土へ——北大に対する遺骨請求と先住権』(北大開示文書研究会編著、緑風出版)、主な論文にUnderstanding the Fishing Rights of the Ainu of Japan: Lessons Learned from American Indian Law, the Japanese Constitution, and International Law(Colorado Journal of International Environmental Law and Policy 2001)、「アイヌ人骨返還を巡るアイヌ先住権について」(『法の科学』45号)などがある。
MORE -
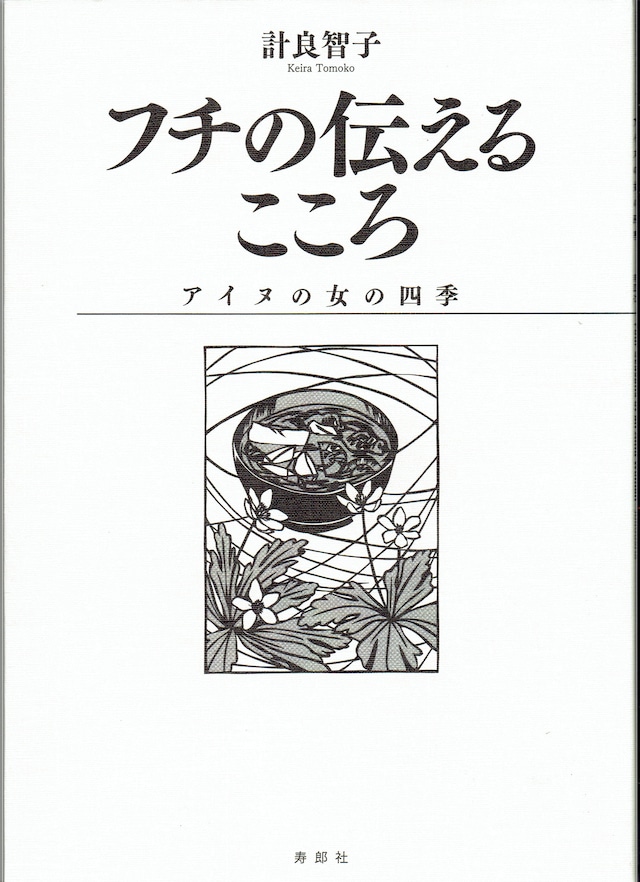
フチの伝えるこころ——アイヌの女の四季
¥2,750
1995年の名著『アイヌの四季』をアイヌ民族文化財団の助成を得て、英訳ページを付け、復刊しました。フチ(アイヌ語で尊敬すべきおばあさんの意)との暮らしのなかで著者が教わった、アイヌのこころや生活の知恵を紹介しています。 オハウやチタタプといったアイヌ料理のレシピも多数掲載されています! 右から開くと日本語版、左から開くと英語版という作りになっています。 計良智子 著 2018年12月刊 B5判/並製/208頁 本体2500円+税〔税込2750円〕 ISBN 978-4-909281-13-5 C0039 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 冬 春 夏 秋 ふたたび冬 おわりに —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 1947年、胆振管内白老町生まれ。「ヤイユーカラの森」運営委員。「ヤイユーカラ・アイヌ民族学会」創設メンバー、後、事務局長も務める。1994年「日本民藝館展」にチタラベ(花ござ)入選。2016年2月逝去。
MORE -

反ヘイト・反新自由主義の批評精神——いま読まれるべき〈文学〉とは何か
¥2,200
“批評”は停滞と閉塞を打ち破る。アイヌ民族・沖縄・原発などをめぐってSNSで欺瞞がはびこり、「極右」「オタク(萌え)」「スピリチュアル」な言説がもてはやされるなかで、気鋭の文芸批評家が放った渾身の“一矢”。 文学界・思想界からの反響・反発が必至の〈禁断〉の文芸評論集。 岡和田晃 著 2018年8月刊 四六判/並製/434頁 本体2000円+税〔税込2200円〕 ISBN 978-4-909281-12-8 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに Ⅰ ネオリベラリズムに抗する批評精神 ◉真空の開拓者——大江健三郎の「後期の仕事」 ◉「核時代の想像力」と子どもの「民話」——『はだしのゲン』への助太刀レポート ◉世界の革命家よ! 孤立せよ! ◉「歴史の偽造」への闘争——『日本人論争 大西巨人回想』 ◉文学に政治を持ち込む戦術の実践——陣野俊史『テロルの伝説 桐山襲烈伝』 ◉高橋和巳、自己破壊的インターフェイス ◉破滅の先に立つ批評——神山睦美『希望のエートス 3・11以後』 ◉「近代文学の終り」と樺山三英「セヴンティ」——3・11以後の〈不敬文学〉 ◉選び取り進むこと——山城むつみインタビュー Ⅱ ネオリベラリズムを超克する思弁的文学 ◉青木淳悟——ネオリベ時代の新しい小説 ◉「饒舌なスフィンクス」からの挑戦状——青木淳悟『匿名芸術家』 ◉『北の想像力』という巨大な〈弾〉 ◉『北の想像力』の試み——「仮説の文学」でネオリベに対峙 ◉『北の想像力』という「惑星思考」——山林に自由存せず、から始まる〈北海道文学〉史の再考 ◉「私」と〈怪物〉との距離——藤野可織の〈リアリズム〉 ◉日常の裏に潜む別世界——小山田浩子『穴』 ◉林美脉子という内宇宙 ◉「作者の死」、パンドラゲートのその先へ——林美脉子『タエ・恩寵の道行』栞文 ◉文学による「報道」——笙野頼子『さあ、文学で戦争を止めよう 猫キッチン荒神』 Ⅲ 北方文学の探求、アイヌ民族否定論との戦い ◉小熊秀雄を読む老作家・向井豊昭を読む ◉夷を微かに希うこと——向井豊昭と木村友祐 ◉アイヌ民族否定論の背景 ◉環太平洋的な「風景」を描いた民族誌——金子遊『辺境のフォークロア』 ◉私たちは『アイヌ民族否定論に抗する』をなぜ編んだか——岡和田晃×マーク・ウィンチェスター ◉北限で詠う詩人たち、「途絶えの空隙」とそこからの飛翔 ◉放射能が「降る降る」現実を前に——小坂洋右『大地の哲学 アイヌ民族の精神文化に学ぶ』 ◉中央の暴力を掻き回す辺境の言葉——向井豊昭『怪道をゆく』 ◉ノッカマップを辿り直して ◉「がんばれニッポンっ!」という空白を埋める——木村友祐『イサの氾濫』 ◉生きられる隙間を探せ——木村友祐『野良ビトたちの燃え上がる肖像』 ◉歴史修正主義に抗する先住民族の「生存の歴史」——津島佑子『ジャッカ・ドフニ』 ◉津島佑子と「アイヌ文学」——pre-translationの否定とファシズムへの抵抗 ◉歴史修正主義と〈マイノリティ憑依〉をともに打破する言葉はどこか——教育者にして作家・向井豊昭の調査と思索、その原点 ◉〈アイヌ〉をめぐる状況とヘイトスピーチ——向井豊昭「脱殻」から見えた「伏字的死角」 ◉「文化振興」に矮小化される「アイヌ政策」を批判、表象と政治のねじれた関係を解きほぐす——計良光範『ごまめの歯ぎしり』 ◉マイノリティ相互の関係史を資料と証言で掘り下げる——石純姫『朝鮮人とアイヌ民族の歴史的つながり』 ◉江原光太と〈詩人のデモ行進〉——『北海道=ヴェトナム詩集』再考 ◉江原光太と〈詩人的身体〉——郡山弘史、米山将治、砂澤ビッキ、戸塚美波子らを受け止めた器 ◉断念の感覚の漂着点——中原清一郎『人の昏れ方』 ◉異議を申し立てる文学——木村友祐『幸福な水夫』 Ⅳ 沖縄、そして世界の再地図化へ ◉沖縄の英文学者・米須興文の「二つの異なった視点」——主に『ベン・ブルベンの丘をめざして』収録文から考える ◉移動と語りの重ね書きによる世界の再地図化——宮内勝典『永遠の道は曲りくねる』 あとがき —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 岡和田晃(おかわだ・あきら) 1981年、北海道上富良野町生まれ。早稲田大学第一文学部卒。筑波大学大学院人文社会科学研究科で修士号を取得。文芸評論家、ゲームデザイナー、東海大学文芸創作学科非常勤講師。「「世界内戦」とわずかな希望——伊藤計劃『虐殺器官』へ向き合うために」で第五回日本SF評論賞優秀賞受賞(2010年度)。2014年、『北の想像力——《北海道文学》と《北海道SF》をめぐる思索の旅』(編集、寿郎社)で第35回日本SF大賞最終候補。2016年、『破滅(カタストロフィー)の先に立つ——ポストコロニアル現代/北方文学論』で第50回北海道新聞文学賞創作・評論部門佳作。2015年の『アイヌ民族否定論に抗する』(共編著、河出書房新社)は広く話題となり、関連して、反ヘイトの評論・公演活動を行なう。 その他の著作に『アゲインスト・ジェノサイド』(新紀元社)、『「世界内戦」とわずかな希望 伊藤計劃・SF・現代文学』(アトリエサード)、『向井豊昭傑作集 飛ぶくしゃみ』(編著、未來社)、『向井豊昭の闘争 異種混淆性(ハイブリディティ)の世界文学』(未來社)、『世界にあけられた弾痕と、黄昏の原郷——SF・幻想文学・ゲーム論集』(アトリエサード)、『石牟礼道子——さようなら、不知火海の言魂』(共著、河出書房新社)など。『エクリプス・フェイズ』(筆頭訳、新紀元社)ほか翻訳書も多数。 日本文藝家協会、日本SF作家クラブ、日本近代文学会、それぞれ会員。
MORE -

近現代アイヌ文学史論⸺アイヌ民族による日本語文学の軌跡〈近代編〉
¥3,190
アイヌ民族によって書かれた文学(小説・評論・詩歌)のすべてを論じた日本初のアイヌ文学通史——その上巻「近代編」がついに完成。 刺激的な内容と五〇〇ページを越えるボリュームで日本文壇と学会、読書界に波紋を呼ぶこと必至の大著! 須田茂 著 2018年4月刊 四六判/並製/528頁 本体2900円+税〔税込3190円〕 ISBN 978-4-909281-02-9 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 序章 一節 「近現代」という時代区分について 二節 近現代のアイヌ民族における「文学」 三節 「アイヌ民族」の範囲 第1章 異言語(日本語)の強制と同化教育 一節 キリスト教によるアイヌ教育 二節 日本政府のアイヌ教育 三節 独立系のアイヌ教育 四節 金成太郎の位置 第2章 樺太からの発信〈その1〉——山辺安之助『あいぬ物語』 一節 山辺安之助の『あいぬ物語』の梗概 二節 『あいぬ物語』の出版経緯 三節 『あいぬ物語』の編集過程 四節 『あいぬ物語』の文学的評価 第3章 樺太からの発信〈その2〉——アイヌの民俗誌 一節 『極北の別天地』——バフンケ、アトイサランデ、シベケンニシの声 二節 千徳太郎治の『樺太アイヌ叢話』 三節 『樺太アイヌ叢話』について 四節 『樺太アイヌ叢話』の謎 第4章 武隈徳三郎の『アイヌ物語』とその周辺 一節 武隈徳三郎の『アイヌ物語』の出版経緯 二節 『アイヌ物語』の内容と意義 三節 知られざる武隈の生涯の解明 第5章 知里幸惠の『アイヌ神謡集』——原風景の創出 一節 知里幸惠の略歴 二節 アイヌ文学史における業績 三節 知里幸惠の文学の鉱脈 四節 『アイヌ神謡集』の波紋 五節 『アイヌ神謡集』の普遍性 第6章 詩歌人たちの登場——内なる越境の始まり 一節 違星北斗の文学と思想 二節 バチェラー八重子の献身 三節 森竹竹市の詩歌と訴え 第7章 近代後期の言論者たち 一節 貝澤藤蔵と『アイヌの叫び』(一九三一年) 二節 貫塩喜蔵(法枕)と『アイヌの同化と先蹤』(一九三四年) 三節 『蝦夷の光』を舞台とした言論(一九三〇〜三三年) 四節 辺泥和郎と『ウタリ乃光リ』(一九三二〜三四年) 五節 川村才登と「アイヌの手記」(一九三四年) 第8章 近代後期のキリスト教系アイヌ文学の系譜——ジョン・バチェラーの弟子たち 一節 『ウタリグス』(一九二一〜二五年?) 二節 『ウタリ之友』 三節 片平富次郎(一九〇〇〜五九年) 四節 向井山雄(一八九〇〜一九六一年) 五節 上西与一(?〜一九四四年?) 六節 知里高央(一九〇七〜六五年) 七節 山内精二(一九一一〜八五年) 八節 江賀寅三(一八九四〜一九六八年) 第9章 内なる越境文学としての近代アイヌ文学 一節 越境文学とは何か 二節 「内なる越境」とその特徴 三節 近代日本とアイヌ民族の「内なる越境」 四節 近代アイヌ文学のテーマとして「同化」と「同化政策」 五節 近代アイヌ文学の声、再び 六節 近代アイヌ文学の特徴と意義——結論として あとがき 主な参考文献 人名索引 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 須田茂(すだ・しげる) 1958年東京都生まれ。学習院大学法学部政治学科卒。民間企業に勤務する傍ら明治以来の近現代のアイヌ文学を研究し、その成果を「近現代アイヌ文学史稿(一)~(八)」として札幌の同人誌『コブタン』に発表。現在同誌に「現代編」を連載している。北海道文化財保護協会会員。神奈川県川崎市在住。 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【正誤表】 『近現代アイヌ文学史論〈近代編〉』の文中に誤りがありました。お詫びして下記の通り訂正いたします。(著者 須田茂) ●25頁7~11行目 誤 北海道アイヌ協会は、「北海道ウタリ協会」であった一九八〇年から自らアイヌ史編纂に着手し、北海道ウタリ協会アイヌ史編集委員会が『アイヌ史資料集』の発行を逐次開始した。現在までに第一期全八巻〔一九八〇年〕、第二期全七巻〔一九八四年〕が刊行されている。これは主に研究資料としての価値を認められた一次資料を収集・編纂したものである。しかしながらこれはあくまで歴史的資料の収録が中心で、アイヌ民族独自の視点に立った歴史観が示されたものではなかった。また一部の差別的視点が問題となった〔註3〕。」 正 北海道アイヌ協会は、「北海道ウタリ協会」であった一九八二年から自らアイヌ史編纂に着手していたが、紆余曲折を経て、北海道ウタリ協会アイヌ史編集委員会が『アイヌ史 資料編』〔第1巻~第4巻〕及び『北海道アイヌ協会・ウタリ協会 活動史編』〔第5巻〕の発行を逐次開始した。これは主に研究・参考資料としての価値を認められた諸資料・所蔵目録等を収集・編纂したものである。しかしながらこれはあくまで歴史的資料の収録が中心で、アイヌ民族独自の視点に立った歴史観が示されたものではなかった。(*1) ●34頁6~10行目 〔註3〕は削除します。 ●48頁4行目 誤 開校した 正 閉校した ●53頁7行目〔 〕内 誤 野村義一『野村義一と北海道ウタリ協会』 正 竹内渉『野村義一と北海道ウタリ協会』 ●88頁7行目(小見出し含む) 誤 説術者 正 説述者 ●89頁13~14行目(小見出し含む) 誤 三人の「説述者」はいずれも樺太から北海道への強制移住者で、北海道での不漁続きにより樺太に帰還したという人たちである。 正 全文削除します。(*2) ●89頁17行目~90頁1行目 誤 もうひとりの「説述者」であるシベケンニシについては山辺安之助の一歳年少であり、対雁で日本語を学んだ可能性がある。 正 全文削除します。(*2) ●149頁2行目 誤 知里高央 正 知里高吉 ●164頁7行目 誤 たち 正 だち ●169頁5行目 誤 津島祐子 正 津島佑子 ●241頁最終行 誤 常任幹事 正 常任監事 ●346頁1行目 誤 副会長 正 副理事長 ●364頁1~2行目 誤 北海道アイヌ協会の理事に就任 正 北海道アイヌ協会の監事、その後理事に就任 ●506頁18行目 誤 野村義一 正 竹内渉 ●521頁(人名索引) 誤 チェフサンマ 正 チュフサンマ 誤 知里高吉 正 149頁を追記 誤 知里高央 正 149頁を削除 誤 津島祐子 正 津島佑子 (*1)北海道ウタリ協会(当時)は河野本道著『アイヌ史資料集』の刊行には関与しておりません。ご指摘ならびにご教示いただきました竹内渉様に感謝いたします。 (*2)削除理由:三人の「説術(述)者」が強制移住者であるとの記述に誤りがあるため。ご指摘いただきましたエンチウ(樺太アイヌ)協会様に感謝いたします。
MORE -

古文書が伝える北海道の仰天秘話51
¥1,980
公文書館、博物館、図書館は〈宝の山〉! 徳川家康の黒印状から幕末の松前藩のクーデターを物語る文書、明治期の人事・政争・汚職の顛末がわかる記録まで—— 「北海道命名150年」の〈光〉と〈影〉も明らかに。 合田一道 著 2018年3月刊 A5判/並製/188頁 本体1800円+税〔税込1980円〕 ISBN 978-4-909281-0-81 C0021 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 まえがき 01 松前家、蝦夷島主の地位固める——徳川家康からの黒印状 02 アイヌ民族の懐柔と隷属化——「夷酋列像」に書かれた序文 03 日露初交渉の陰で消えた命——ヲロシャ人小屋外廻り之図 04 「噴火湾」と名付けたイギリスの探検船——「魯西亜船入津一件」に見るもう一つの異国船騒動 05 北海道初の官製道路、開削——近藤重蔵の偉業を伝える「東蝦新道記」 06 苫小牧に伝わる八王子千人同心隊の苦難——幽霊話を生んだ「梅の墓」の七言絶句 07 津軽藩士、斜里警備で大量死——生き残った藩士が伝えた壮絶な記録 08 心中事件を伝える「悲恋塚」——真相を隠蔽する「近藤家古文書」 09 ペリー艦隊の来航で松前藩が大騒ぎ——住人を震え上がらせた「箱館入港亜米利加船触書」 古文書コラム1——坂本龍馬らの人相書き手配書 10 幕末に「ストーブ」の図面描く——幕吏梨本弥五郎の発注文書 11 野村半島で和人が畑作——作った野菜を記録した「加賀屋氏大宝恵」 12 「唐人お吉」ならぬ「唐人たま」の記録——絵入りで残された「ライス箱館応援録」 13 新政府発足直後に小樽で暴動——旧幕府役人で記した「穂足内村騒立一件書類」 古文書コラム2——箱館の「遊女屋一覧表」 14 新政府の誕生と松前藩内の対立——箱館府知事・清水谷公考が詠んだ和歌 15 松前藩、血のクーデター——激動の時代を伝える「正議隊建白書」 16 箱館へ向かった榎本武揚の決意——江戸を脱走の直前、勝海舟らに便り 17 外国人の殺害・暴行を戒める——太政官が峠下集落に掲げた高札 18 判然としない土方歳三の最期——流れ玉説・戦闘説などあり遺体も不明 古文書コラム3——土方歳三の優しい文学 19 息子二人と戦死の覚悟——開陽丸機関長中島三郎助が妻に便り 20 アイヌ民族に寄り添う姿勢を地名に——松浦武四郎の蝦夷地名選定の上申書 21 漢詩で伝える開拓初期の様子——島義勇の「北海道紀行草稿」 22 大友亀太郎、開拓使へ仕官望まず——実母の看護が理由の“辞職願” 古文書コラム4——「宝庫」のナンバーワンは黒田清隆 23 仙台藩岩出山領の北海道移住——村の憲法「邑則」に込められた決意 24 移住者の草小屋に火を放つ——開拓判官・岩村通俊の「御用火事」の記録 25 「赤い星」のマークはいつ生まれた?——蛯子末次郎考案の「北辰旗」 26 定山渓温泉の開祖は公務員?——開拓使が美泉定山を採用した文書 古文書コラム5——美泉定山の死を伝える過去帳 27 村橋久成とサッポロビール——「開拓使麦酒醸造契約書」 古文書コラム6——村橋久成の「香典帳」 28 月三回、均一料金で全国に配達——北海道で郵便制度を始める布告案 29 課税強化で漁民の不満爆発——「檜山騒動」の発端となった嘆願書 30 幌内鉄道開業式のハプニング——皇族の訃報で急遽延期の電報 31 黎明期の道路名を知っていますか?——「触書案」が定めた札幌の通り名 32 幕末期から豊平川で渡し守——志村鉄一に対する刑法局の「御指令案」 33 屯田兵制度ができた理由とは?——「屯田兵備設置の建議」 34 函館で起きた外国人殺人事件——ドイツ領事暗殺を記した「断刑伺録」 35 大金で雇われたクラーク博士——開拓判官の外務丞宛の採用記録 36 樺太アイヌ冷遇で憤怒の退職——松本十郎の「職務御免奉願候書」 37 炭鉱開発が北海道開拓の主役に——榎本武揚の幻の調査報告「石炭山取調書」 38 尾張徳川家の入植と「ある事件」——開拓史の古文書「愛知県士族移住事件」 古文書コラム7——新選組の生き残り、永倉新八 39 函館で道内初の新聞発刊——北海道の新聞ことはじめ 40 囚人を酷使する集治監獄の建設——過酷な労働を決めた「北海道巡視意見書」 41 近代汚職の始まりを示す文書——「開拓史官有物払い下げ」の取り消し 42 「札幌県」「函館県」「根室県」があった——わずか四年間の北海道三県一局時代の記録 43 秩父事件の井上伝蔵の最期——死刑判決を受けても偽名で生き抜く 44 執念でできた国道一二号の原型——岩村通俊、高畑利宣の上川開発計画 45 幻に終わった上川離宮構想——永山武四郎に引き継がれた計画の上申書 46 日清戦争から生まれた第七師団——屯田兵制度の廃止を告げる「師団歴史」 47 道民には選挙権がなかった?——全道での投票が実現した「閣議決定書」 48 公衆電話を設置した白虎隊の生き残り——「北海道物産共進会事務及審査報告」 49 アイヌ民族を苦しめた悪法——「北海道旧土人保護法」をめぐる文書 50 知里幸恵に宛てた励ましの便り——金田一京助が『アイヌ神謡集』の出版に際して 51 脱獄魔から劇団の座長に転身——五寸釘寅吉の「釈放指揮書」 古文書から漂う歴史の匂い——あとがきに代えて 参考文献 人名索引 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 1934年北海道上砂川町生まれ。佛教大学文学部卒。北海道新聞社に入社し、道内各地を回る。在職中からノンフィクション作品を発表。退職後は札幌大学講師など。主な作品は『死の逃避行——満州開拓団27万人』『流氷の海に女工節が聴える』『咸臨丸 栄光と悲劇の5000日』『裂けた岬』『日本史の現場検証』『日本人の遺書 1858~1997』『古文書に見る榎本武揚——思想と生涯』『松浦武四郎 北の大地に立つ』など。北海道ノンフィクション集団代表。日本脚本家連盟北海道支部長。ほっかいどう学を学ぶ会顧問。
MORE -

朝鮮人とアイヌ民族の歴史的つながり——帝国の先住民・植民地支配の重層性
¥2,420
戦時下の北海道で過酷な労働を強いられ逃げた朝鮮人をアイヌの人々は匿い続けた。丹念な調査から見えてきた知られざるマイノリティの歴史。〈近現代アイヌ史〉〈在日コリアン形成史〉に一石を投じる本。 石純姫 著 2017年7月刊 四六判/上製/208頁 本体2200円+税〔税込2420円〕 ISBN 978ー4ー902269ー99ー4 C0021 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第一章 前近代期における朝鮮人とアイヌ 第二章 近代期における朝鮮人とアイヌ 第三章 近代期の朝鮮人労務動員とアイヌ 第四章 記憶の表象の暴力 第五章 先住民支配と植民地主義 第六章 サハリンにおけるアイヌと朝鮮人 第七章 戦後におけるアイヌ民族と朝鮮人 第八章 帝国主義の残滓——忘却の力学 結び 聞き取り資料 あとがき —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 石純姫(ソク・スニ) 1960年東京生まれ。中央大学大学院文学研究科博士後期課程修了。現在、苫小牧駒澤大学国際文化学部教授。東アジア歴史文化研究所所長。大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員。
MORE -

シャクシャインの戦い
¥2,750
1669年6月、幕府を揺るがす〈アイヌの一斉蜂起〉が始まる。シャクシャインとは誰か。その時蝦夷地ではなにが起きていたのか——。シャクシャインの戦いを40年調査してきた著者が近世最大の民族戦争の謎を解き明かす。 平山裕人 著 2016年12月刊 四六判/上製/328頁 本体2500円+税〔税込2750円〕 ISBN 978ー4ー902269ー93ー2 C0021 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第一章 松前藩の成立 第二章 シャクシャインの青年期 第三章 シャクシャインの決起 第四章 クンヌイの決戦 第五章 シャクシャインが謀殺される 第六章 後志海岸の抵抗 第七章 ハウカセ外交 第八章 サンタン交易圏とラッコ交易圏 第九章 シャクシャインの戦いと現代 あとがき 注(史料原文) 引用・参考文献 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 平山裕人(ひらやま・ひろと) 1958年(昭和33年)、北海道小樽市生まれ。1981年(昭和56年)、北海道教育大学卒業。現在、北海道小樽市立高島小学校勤務。主な著書に『アイヌ地域史資料集』『ワークブック アイヌ・北方領土学習にチャレンジ』『アイヌ語古語辞典』『アイヌの歴史——日本の先住民族を理解するための160話』(以上、明石書店)、『アイヌ史を見つめて』『アイヌの学習にチャレンジ』『アイヌ史のすすめ』『ようこそ、アイヌ史の世界へ』(以上、北海道出版企画センター)などがある。
MORE -

北の学芸員とっておきの《お宝ばなし》——北海道で残したいモノ伝えたいコト
¥1,650
全道各地の博物館・資料館の学芸員たちが“おらが町のちょっとイイ話”“自慢の所蔵品”について熱く語った1冊。北の自然と文化と人間にまつわる選りすぐりの49編を集めた“北海道ウンチク本”の決定版。 北海道博物館協会学芸職員部会 編 2016年11月刊 四六判/並製/360頁 本体1500円+税〔税込1650円〕 ISBN 978ー4ー902269ー92ー5 C0039 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第1章 謎を秘めた北海道の生き物たち 第2章 プレート衝突が生み出した大地に眠るもの 第3章 天空に広がる星と月 第4章 ワイズユース・自然と人間の関わり 第5章 大地が育む人のおおらかさ・あたたかさ 第6章 北の大地で活躍した人々 第7章 北海道の戦争の記憶 第8章 地域に残る先祖伝来の風習 第9章 アイヌ語地名とアイヌ文化の伝承 第10章 遺跡から見えてくる古代の文化・風習 第11章 まちの記憶と文化を刻む古い建物や資料 あとがきに代えて —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【編者略歴】 北海道博物館協会学芸職員部会 北海道内各地の博物館・美術館・動物園・水族館等に勤務する学芸員有志が集う専門職集団。 北海道博物館協会(1961年〜)に属し、研修活動の場を通じて学芸職員としてのスキルアップと情報共有に取り組むと共に、学芸員それぞれの専門分野を生かして博物館相互の交流・連携を推し進めている。 1977年の設立で2016年に40周年を迎えた。会員数は約180名。
MORE -

ごまめの歯ぎしり
¥2,860
北海道から世界に向けて〈アイヌ文化〉や〈先住民の権利〉について発言し続けてきた著者の20年わたる反骨のコラム集。 計良光範 著 2016年3月刊 四六判/上製/464頁 本体2600円+税〔税込2860円〕 ISBN 978ー4ー902269ー86ー4 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 〈はじめに〉と解題 一 これがアイヌ刺繍か——大滝村ドライブインの展示 二 ついに「焚書」か——長見義三の小説『アイヌの学校』 三 最新、最悪の博物館——旭川博物館 四 「熊牧場」へ行った——登別クマ牧場 五 部落差別は北海道にも現存する——西本願寺札幌別院差別落書事件 六 平和な国の恐怖劇——オウム真理教と阪神大震災 七 いま「市民」は——映画『ハーヴェイ・ミルク』 八 演劇評論家ではないけれど——学校祭のための脚本と某専門劇団の脚本 九 再び部落差別の存在について——差別落書きは続いた 一〇 船戸与一『蝦夷地別件』のこと ほか —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 計良光範(けいら・みつのり) 1944年、北海道蘭越町生まれ。《ヤイユーカラの森》運営委員長、北海道教育大学非常勤講師を務めた。 著書に『アイヌ文化の実践——《ヤイユーカラの森》の二〇年(上・下)』『アイヌ社会と外来宗教——降りてきた神々の諸相』(以上、寿郎社)、『北の彩時記』(コモンズ)、『ハンドブック 国際化のなかの人権問題〔第4版〕』『新版 近代化の中のアイヌ差別の構造』『アイヌの世界』(以上、明石書店)、『講座 差別の社会学 第4巻 共生の方へ』(弘文堂)がある。 2015年3月、がんのため逝去。享年71。
MORE -

おれのウチャシクマ
¥2,200
朝鮮人の父とアイヌの母をもつ元北海道ウタリ協会理事の小川隆吉が初めて語ったその生い立ちと戦後の民族運動——。大日本帝国が生んだアイヌの闘いの人生を写真とともに記録した本。 小川隆吉 四六判/並製/208頁 ISBN978ー4ー902269ー83ー3 C0036 2015年10月刊
MORE -

ウレシパ物語——アイヌ民族の〈育て合う物語〉を読み聞かせる
¥1,870
2014年に亡くなった北海道出身の画家藤野千鶴子の挿し絵が楽しい親子で読めるアイヌの民話19編。自然(神々)とともに生きたアイヌ民族の怖い話、悲しい話、愉快な話をわかりやすい話し言葉で。 富樫利一 著 2015年9月刊 四六判/上製/192頁 本体1700円+税〔税込1870円〕 ISBN 978ー4ー902269ー79ー6 C0039 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに——語り継がれてきた雄大な物語に魅せられて シンタは宇宙船——ポイヤウンペの物語 有珠岳に祈る 大津波と兎——オレプンペとイセポ 鳥と熊蜂の大戦争——パシクルとチッソヤカムイ シシャモの伝説 フンペ山物語——ショキナとエサマンカムイ 川下の爺さんと川上の爺さん——パナンペとペナンペ 悪いカムイ——ウエンカムイ 柳の葉が魚になった——シシャモの誕生 登別温泉のカムイ モモンガ沼 プクサとトウレプのカムイ あの世の入り口——アフンパロ 海のカムイの贈り物 けがらわしや! きたならしや! 鯱のカムイと嫁を争う 太郎のヤイサマ——幌別アイヌの伝承 エカシのさくら 珍地名となってしまったアイヌ語 藤野千鶴子さんのこと——あとがきにかえて —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 富樫利一(とがし・としかず) 1932年(昭和7年)北海道生まれ。夕張北高等学校卒業後、登別市役所勤務をへて、現在、アイヌ文化アドバイザー。アイヌ文化とアイヌの自立・復興についての講演を全国で行なっているほか、子どもたちへのアイヌ口承文学の読み聞かせ活動にも長年取り組む。 『維新のアイヌ 金城太郎』(未知谷)、『伏流』『風に祈る』『血価の証言』(以上、彩流社)など著書多数。
MORE -

永久保秀二郎の『アイヌ語雑録』をひもとく
¥2,860
100余年前、春採アイヌ学校の教師・伝道師の永久保秀二郎がいきいきと記録した当時のアイヌの〈言葉〉と〈伝承〉。その貴重な記録を読み解いたアイヌ語・アイヌ文化研究に資する労作。アイヌ語辞典としても実用的。 中村一枝 編注 2014年12月刊 A5判/並製/324頁 本体2600円+税〔税込2860円〕 ISBN 978ー4ー902269ー73ー4 C0039 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 寄贈文書類目録 『アイヌ語雑録』解題 凡例 出典及び参考文献 語彙の部 アイヌ語未記載の語 伝承の部 1. アイヌの教訓 2. カムイノミシノツサア 3. タプカラ 4. アイヌの伽噺 5. 明治天皇崩御 6. カムイラン 7. ウララシュイ 8. ホイヤホイヤ 9. 歌謡以外 アイヌ語方言の地域性 1. 日高東半部、北海道東部・北部のアイヌ語方言に包含すると思われる語 2. 日高西半部、胆振、北海道中・西南部のアイヌ語方言に包含すると思われる語) 参照文献の影響 1. 近世の文献類と近似性が高い語 2. バチラー辞典の語と近似性が高い語 日本語—アイヌ語索引 『永久保秀二郎の『アイヌ語雑録』をひもとく』によせて⋯⋯奥田統己 おわりに —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【編者略歴】 中村一枝(なかむら・かずえ) 1931年(昭和6年)北海道釧路市に生まれる。北海道学芸大学2類修了。日本大学文学部卒業。釧路市役所職員、釧路市立共栄中学校教諭、釧路短期大学附属高等学校非常勤講師を勤める。釧路アイヌ文化懇話会、札幌女性史研究会会員。
MORE -

アイヌ文化の実践——《ヤイユーカラの森》の二〇年(下)
¥3,850
古老から教わったアイヌの知恵を、今を生きる力に変える——。アイヌも和人も一緒に学ぶ小さな会の大きな記録。現在のアイヌをめぐる状況が分かる本。 計良光範 編 2014年11月刊 A5判/並製/716頁 本体3500円+税〔税込3850円〕 ISBN 978ー4ー902269ー74ー1 C0039 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに——《ヤイユーカラの森》について 【ヤイユーカラ宣言】 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 アイヌ史略年表 おわりに——次の活動に向けて 索引 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【編者略歴】 計良光範(けいら・みつのり) 1944年、北海道蘭越町生まれ。《ヤイユーカラの森》運営委員長、北海道教育大学非常勤講師を務めた。 著書に『アイヌ社会と外来宗教——降りてきた神々の諸相』(以上、寿郎社)、『北の彩時記』(コモンズ)、『ハンドブック 国際化のなかの人権問題〔第4版〕』『新版 近代化の中のアイヌ差別の構造』『アイヌの世界』(以上、明石書店)、『講座 差別の社会学 第4巻 共生の方へ』(弘文堂)がある。
MORE -

アイヌ文化の実践——《ヤイユーカラの森》の二〇年(上)
¥3,300
アイヌも和人も北海道で一緒に学ぶ《ヤイユーカラの森》の活動記録から「自然と人間」「生活と文化・芸術」「先住民と植民者」などについて考えるための本。 計良光範 編 2014年3月刊 A5判/並製/540頁 本体3000円+税〔税込3300円〕 ISBN 978ー4ー902269ー68ー0 C0039 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに——《ヤイユーカラの森》について 【ヤイユーカラ宣言】 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 アイヌ史略年表 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【編者略歴】 計良光範(けいら・みつのり) 1944年、北海道蘭越町生まれ。《ヤイユーカラの森》運営委員長、北海道教育大学非常勤講師を務めた。 著書に『アイヌ社会と外来宗教——降りてきた神々の諸相』(以上、寿郎社)、『北の彩時記』(コモンズ)、『ハンドブック 国際化のなかの人権問題〔第4版〕』『新版 近代化の中のアイヌ差別の構造』『アイヌの世界』(以上、明石書店)、『講座 差別の社会学 第4巻 共生の方へ』(弘文堂)がある。
MORE -

まつろはぬもの——松岡洋右の密偵となったあるアイヌの半生
¥3,080
満鉄に売られたコタンの天才少年。英才教育を受け憲兵となった少年は松岡洋右の命を受け「中国人」として大陸に放たれる。任務は“日本軍の非道を暴くこと”。実在の諜報員・和気市夫ことシクルシイの衝撃の自伝。 シクルシイ 著 2010年11月刊 四六判/並製/448頁 本体2800円+税〔税込3080円〕 ISBN 978ー4ー902269ー40ー6 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 四月二十九日 オビラメ ノ・メ・ク・タ 谷間の家 竹筒 樺太へ 郵便配達 審問 ハルピンへ スンガリーの四季 北京へ 異邦の旅 ハリウッドの下水道 相沢中佐 故郷へ 銀貨 長江の仲間たち 砕けた馬 逮捕 闇の穴 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 シクルシイ(和名・和気市夫) 1918年(大正7年)4月29日、北海道屈斜路湖畔のコタンに生まれる。父は和歌山県出身の和人、母はコタンのエカシ弟子小太郎の娘。和名・和気市夫。 生後間もない頃から神童として知られ、それに目をつけた南満州鉄道理事の松岡洋右に選ばれ、英才教育を施される。4歳で高等小学校2年に編入、8歳で旭川商業学校2年に編入し仏・露・中国語などを学ぶ。 1929年(昭和4年)、11歳で満鉄傘下のハルピン学院に入学、英・仏・露・中の言語以外にモンゴル語・ラテン語・ギリシャ語などを学び、同時に体術・銃器・爆薬・無線通信・暗号などの教育を受ける。 1931年(昭和6年)、13歳でロックフェラー財団に属する北京の燕京大学人類学部多言語科に入学。「薫之祥(クン・ズシアン)」の中国名で主に学術調査を行いながら、中国・中央アジア・アフリカ・アメリカの各国を回る。この間に「北千島アイヌ語」に関する博士論文を書く。 1938年(昭和13年)、20歳の時に帰国して陸軍情報部付少尉となり、松岡の命を受けてアジア各地で「日本軍の戦闘中に起こった暴虐行為の真偽の調査」などを1945年(昭和20年)まで行なう。 1945年8月16日、中華民国政府公安部によって逮捕され、拷問・土牢拘置を経て、46年、東京国際軍事法廷での松岡洋右(戦犯容疑)の重要参考人兼戦犯容疑者としてアメリカに引き渡されるが、松岡の死去により不起訴となる。 戦後はGHQ本部で軟禁状態で働かされた後、第一生命保険相互会社の人権問題研修推進本部理事会の顧問などを務めた。 2000年(平成12年)10月23日、肺気腫で死去。享年82。
MORE