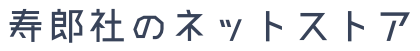-


青い記念碑 教えるとは希望を語ること⸺1960年代の北見北斗高生・札幌開成高生への〈ことば〉と小池喜孝先生のこと
¥2,200
ルイ・アラゴン、ロマン・ローラン、ゴーリキー、ドストエフスキー、ジャン・タルデュー、竹内好、丸山眞男、堀田善衛、中野重治、古在由重、小池喜孝…… 「60年安保」の熱気が冷めやらぬ北海道の高校で、そのとき教師は何に悩み、何を生徒に伝えたのか⸺先人たちの〈勁いことば〉によって自他と真摯に向き合った国語教師の北見・札幌での青春の記録。 森山弘毅 著 2025年9月刊 四六判/上製/108頁 本体2000円+税〔税込2200円〕 ISBN 978-4-909281-71-5 C0037 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 まえがき I 北見北斗高と札幌開成高の生徒たちへ ルイ・アラゴンとロマン・ローラン―私の生活信条 「記憶から」と「記憶を超えるもの」 「修身」と「非国民」の記憶 人間の声を聞く 十五年戦争と堀田善衛の思想 アイヒマンに対する立場 うたについて―「はやり歌」と「防人の歌」 古事記歌謡のヘソなし解釈 「はやり歌」と「防人の歌」 共同の生活意識と類同の世界 北見を去るにあたって こもごもの思い 朝鮮戦争と「コミット」 堀田善衛の言葉 古在由重の『戦中日記』 軍国主義の言葉 真の「愛国心」とは K君、「わらび座」は君の大学だ 「わらび座」というふるさと 「学力テスト」をめぐる「手記」 僕自身のもどかしさ 「わらび座」の舞台 Ⅱ 一九六〇年代の北見北斗高校 六〇年代前半の北見北斗高と小池喜孝先生―追悼・小池喜孝先生 基本姿勢を形作った北見北斗の四年間 小池喜孝先生の赴任 小池喜孝先生の「伝説」 『鼓動』と「私の戦后史」 尾崎秀実『愛情はふる星のごとく』に関わる 「文武両道」の中で 高教組役選時の「策戦会議」 「集団の中の私」というテーマ 「井上伝蔵」と小池喜孝先生 小池喜孝先生の「仲人口」 北見北斗高「三八期生」の私 あとがき —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 森山弘毅(もりやま・こうき) 1937年(昭和12年)、京都市生まれ。1960年(昭和35年)、北海道大学文学部(国文学專攻)卒業。北見北斗高校・札幌開成高校の国語科教員を経て苫小牧高専教授、釧路公立大学経済学部教授。2003年(平成15年)、釧路公立大学名誉教授。日本歌謡学会会員。著書に『新日本古典文学大系62 田植草紙・山家鳥虫歌・鄙廼一曲・琉歌百控』(共著、岩波書店)、『金素雲「朝鮮民謡選」と日本の歌謡『』菅江真澄「鄙廼一曲」小論集』(いずれも無明舎出版)、『随想集窓の内そと』『回想録私の戦中戦後体験』(いずれも一耕社)がある。
MORE -


高校「公共」副読本 高校生と探究したい北海道の地域課題
¥2,310
2022年に新設された高校の科目「公共」。 本書は公共の抽象的なテーマを北海道の社会問題に引き寄せて具体例を挙げながら伝える、道内の教師・塾講師待望の副読本です。 高校生が自習用に使用することもできます。 前田輪音編 A5判/並製/168頁 本体2100円+税〔税込2310円〕 ISBN 978-4-909281-66-1 C7030 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次より】 第1部 多様な地域課題と向き合うための予備知識 第1章 北海道の概要 第2章 北海道の重要な裁判 第2部 北海道の地域課題 第1章 産業とエネルギー—くらしに直結する課題 第2章 人権—人間らしく生きるための安全・安心・自由 第3章 平和と自由—くらしと国家が対立するとき 第3部 学校の外とのつながりを利用した学び 第1章 現地で学ぶ 第2章 専門家との授業づくり 第3章 博物館・資料館の有効利用 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者】 前田輪音(まえだ・りんね) 北海道札幌市出身、在住。北海道教育大学教職大学院准教授。社会課題に向き合い解決を目指す人の育成を目標として、北海道の憲法問題を扱う教材を開発している。全国民主主義教育研究会会長、北海道公民教育学会副会長。
MORE -

知られざる〈学童保育〉の世界——問題だらけの“社会インフラ”
¥2,090
「小一の壁」だけではない ギュウギュウ詰めの子どもたち、結婚をあきらめるワーキングプアの職員、「学童ガチャ」で苦しむ親子、補助金ビジネスで儲ける企業……。 問題だらけの“社会インフラ”の内幕。 学童保育運営支援アドバイザー 萩原和也 著 2024年7月刊 四六判/並製/244頁 本体1900円+税〔税込2090円〕 ISBN 978-4-909281-60-9 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに——学童保育とは何か 第1章 小一の壁——学童保育の現実 1 「小一の壁」とは 2 小一の壁がもたらす悲劇 3 学童保育の“壁”の増加 4 軽視されてきた「お弁当の壁」 5 小一の壁問題の複雑さ 6 小一の壁を乗り越えるための秘策 7 自治体に期待したい小一の壁解消 第2章 正統派学童と学童そっくりさん事業——学童保育の実態 1 多様な学童保育のあり方 2 学童保育の中心——放課後児童クラブ 3 放課後児童クラブ以外の学童 4 放課後児童クラブの理想と現実 コラム 学童保育に関する用語の解説 第3章 学童の世界が複雑になったわけ——学童保育の歴史 1 民から生まれたアウトロー的存在 2 地域ごとに独自の進化——「あってよかった学童保育」の時代へ 3 少子化対策で注目される学童保育 4 位置づけが大きく変化——「あって当たり前」の時代に 第4章 「子どもをあきらめた」の衝撃——学童保育の貧困 1 「子どもをあきらめた」という投稿 2 避けられなかった低賃金構造 3 少なすぎる国の補助金 4 運営予算の不足 5 職員の貧困を加速させる補助金ビジネス 第5章 親と事業者を苦しめているもの——学童保育の諸問題 1 報道される事件・事故は氷山の一角 2 とにかく人手不足 3 ギュウギュウ詰めの学童保育 4 暴れてキレる子どもたち 5 学童にはびこる「やりがい搾取」 6 保護者の負担感と法的リスク 7 問われる学童職員の資質 8 コンプライアンスとリスクマネジメント 第6章 学童ガチャの悲劇——学童保育の選択 1 学童ガチャの実態 2 学童ガチャ対策の第一歩——学童保育所をよく調べる 3 学童保育所でどう過ごすことになるか 4 学童保育所にも性格がある 5 子どもの「行き渋り」 第7章 小さな学童保育所を訪ねて——学童保育の理想 1 すべてが手作り——福島県浅川町のアットホームな小さなクラブ 2 あえて打ち出す学習支援 3 勉強漬けではない子どもたち 4 さらなる認知が課題 5 民設にこだわる北海道札幌市の小さなクラブ 第8章 こどもまんなか社会における役割——学童保育の進化 1 「こどもまんなか社会」は始まったけれど 2 こどもまんなか社会の中の放課後児童クラブ 3 放課後児童クラブの資格強化 4 学童保育の貧困を防ぐための仕組み 5 児童虐待防止・不登校対応・孤育て解消 6 子どもの貧困対策で果たすべき役割 7 子どもの人権を守る砦として あとがき —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 萩原和也(はぎわら・かずや) 1970年、東京都生まれ。中央大学法学部卒。産経新聞記者を経て、2011~22年、NPO法人あげお学童クラブの会代表理事等、運営事業者として学童保育所の運営に携わる。2019~21年、埼玉県学童保育連絡協議会の副会長を務める。2023年、日本で唯一の学童保育所の運営支援を行う非営利法人「あい和学童クラブ運営法人」を設立。現在、学童保育運営支援アドバイザー。あい和学童クラブ運営法人のサイト:https://aiwagakudou.com/
MORE -

北海道大学もうひとつのキャンパスマップ——隠された風景を見る、消された声を聞く
¥1,760
※ポプラ並木やクラーク博士は載ってません アイヌコタン、植民地主義、軍事研究…… 札幌のド真ん中に位置する“観光名所”北海道大学札幌キャンパスには、大学が積極的に語ろうとしない〈歴史〉がある—— 有志教員と学生が外部の研究者にも協力を仰いで完成させた、北大の知られざるもうひとつの歴史ガイド。 「開拓150年」「ウポポイ開設」「オリンピック招致」に湧く今こそ身につけておきたい、これからの北海道を考えるうえで重要な視点の詰まった一冊。 北大ACMプロジェクト 編 2019年6月刊[初版] 2024年6月刊[第2版] 四六判/並製/208頁 本体1600円+税〔税込1760円〕 ISBN 978-4-909281-15-9 C0026 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 [I かつての風景を想像してみる] あるアイヌ遺骨のふるさと⋯⋯小田博志 コトニ・コタンと琴似又市氏⋯⋯谷本晃久 恵迪寮の地下に眠る農耕集落⋯⋯高瀬克範 植物園の竪穴住居跡⋯⋯高瀬克範 アイヌ音楽に影響を受けた伊福部昭⋯⋯前川公美夫 [II 北大の植民地主義を考える] 1015人が眠るアイヌ納骨堂⋯⋯植木哲也 佐藤昌介の植民学講座⋯⋯番匠健一 林善茂によるアイヌ差別講義事件⋯⋯植木哲也 「国際社会」における新渡戸稲造⋯⋯小山田伸明 新渡戸稲造と植民地台湾の農民⋯⋯張易臻 古河講堂と足尾銅山鉱毒事件⋯⋯小田博志 古河講堂「旧標本庫」人骨放置事件⋯⋯井上勝生 開拓使仮学校と東京イチャルパ⋯⋯関口由彦 [III 北大と戦争の関わりを知る] 大本営門標と行在所門標⋯⋯阿知良洋平 スパイに仕立て上げられた北大生と英語教師⋯⋯立木ちはや 北大工学部の軍事研究⋯⋯山形定 軍事研究に関する議論を巻き起こした中谷宇吉郎⋯⋯笹岡正俊 憲法裁判と学生に向き合った深瀬忠一⋯⋯前田輪音 [Ⅳ 大学と学問のあり方を問う] 森林科初代教授・新島善直の足跡⋯⋯小池孝良 演研青テント撤去事件——大学の土地・施設利用をめぐる闘い⋯⋯桃井希生 北大初の女子トイレの設置を求めて⋯⋯下郷沙季 大学を開く——アイヌ学/和人学をめざして⋯⋯モコットゥナㇱ 先住民と大学の関係を考える——カナダの事例から⋯⋯近藤祉秋 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【編者略歴】 北大ACMプロジェクト 北海道大学の埋もれた歴史を掘り起こし、ACM(オルタナティブ・キャンパス・マップ)を制作するために集まった北大の有志教員と学生のグループ。
MORE -

「九九」が言えないまま大人になる子どもたち[寿郎社ブックレット7]
¥880
子どもたちの不登校・自殺の増加、教員の病欠・早期退職・なり手不足……。 2006年の安倍政権が〈戦後教育〉を破壊し出してから18年—— その“成果”が今、こんなふうに現れている!! 平山裕人 著 2024年1月刊 A5判/並製/80頁 本体800円+税〔税込880円〕 ISBN 978-4-909281-57-9 C0037 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに——断末魔の教育現場 1 教育現場で起きていること 2 何が何でもデジタル化 3 かけ算「九九」が言えない小学生の続出 4 「繰り上がりのあるたし算」「繰り下がりのある引き算」がわからない子ども 5 おもしろくない学びの極致―三・四年生の社会科 6 おもしろくない学びは理科も同じ 7 国語嫌いが増えている 8 中学校に行く前に英語嫌いに 9 学級づくり 10 小一ギャップ 11 中一ギャップ 12 戦後教育の初心に帰る —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 平山裕人(ひらやま・ひろと) 1958年、北海道小樽市生まれ。北海道教育大学卒。1981年から小学校教員となり、北海道内の小学校数校に勤務したのち、2019年に定年退職。現在、小樽市の自宅でひっそりと私塾をする。『だれも「おかしい」と言わない小学校〈超管理教育〉の実態』『シャクシャインの戦い』(以上、寿郎社)、『アイヌ地域史資料集』『ワークブック アイヌ・北方領土学習にチャレンジ』『アイヌ語古語辞典』『アイヌの歴史——日本の先住民族を理解するための160語』(以上、明石書店)、『アイヌ民族の現在、過去と未来!』『人間の歴史入門』(以上、藤田印刷エクセレントブックス)など著書多数。
MORE -

北海道大学発展の歴史とSDGs[エルムブックレット1]
¥1,100
国連SDGsに対する大学の社会貢献度が「国内第1位」「 世界第10位」(THEインパクトランキング2022)となった北大の〈力〉の源泉とそのさまざまな取り組みを解説 横田篤 著 2023年6月刊 A5判/並製/56頁 本体1000円+税〔税込1100円〕 ISBN 978-4-909281-51-7 C0030 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 第一章 SDGsに対する北海道大学の基本方針 はじめに 相互にリンクする一七の目標 大学に求められる姿 THEインパクトランキングの四つの指標と評価方法 土地や空間の利用法を定めたキャンパスマスタープラン サステイナビリティへの意識の高まり グリーン・スマート・サステイナブルキャンパス 大学としての明確なビジョン 第二章 SDGs達成に向けた具体的取り組み 新渡戸氏の意志を継いで SDGsを学ぶカリキュラム 2番「飢餓をゼロに」 14番「海の豊かさを守ろう」 15番「陸の豊かさも守ろう」 17番「パートナーシップで目標を達成しよう」 地球環境科学で気候変動に対策を 農林水産業で地域とともに 第三章 北海道大学を持続可能にする豊かな財産 自主・自立・独立のクラーク精神 独特な全人教育 “北大育ての親”佐藤昌介 アメリカ式の大学運営 日本の大学演習林の約六割を所有 演習林で資金を工面し総合大学へ おわりに——物的財産と知的財産の両輪で —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 横田篤(よこた・あつし) 1957年、東京都生まれ。1984年、北海道大学大学院農学研究科農芸化学科専攻博士後期課程修了(農学博士)後、味の素株式会社中央研究所勤務。1989年、農学部助手として北海道大学に戻り、2000年、大学院農学研究科教授となる。2015〜2019年、農学研究院長。2020年より北海道大学理事・副学長、サステイナビリティ推進機構SDGs事業推進本部長。
MORE -

〈聞き書き〉新しい家族のカタチ——子どもを迎える/育てる女性カップルたち[寿郎社ブックレット5]
¥1,210
政治家秘書によるLGBT差別発言、形ばかりで中身が伴わないパートナーシップ制度、出生数80万人割れの少子化……そのすべてに関わる子育てする女性カップルの〈表〉には出てこなかった〈生の声〉を伝える本。 遠藤あかり・大島寿美子 著 2023年3月刊 A5判/並製/112頁 本体1100円+税〔税込1210円〕 ISBN 978-4-909281-52-4 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 プロローグ 疑問の答えを見つけたくて 第1章 五〇代で女性パートナーとともに五歳の子どもを育てる〈まーりんさん〉の話 自分自身のセクシャリティ/パートナーとの出会い/シリンジ法で子どもを迎える/二人の人から精子提供を受けて/親戚として出産に立ち会う/子育て/子どもにどう伝えるか/二人の教育方針/五〇代——おばあちゃん世代の子育て/子育ての面白さ/法的に守られていない同性カップルの親子関係/周囲との関わり方/家族の証明——パートナーシップと公正証書/同性にも結婚の選択肢を/うちにパパはいない——子どもから見た家族/息子はおそらく出自のことで悩まない 第2章 四〇代で女性パートナーとともに二人の子どもを育てる〈マミーチャンヌさん〉の話 二〇代での結婚と離婚/今の家族になるまで/子どもたちへのカミングアウト/カミングアウトのきっかけ/子どもたちに受け入れてもらえるかどうか/うちはママが二人——パートナーと子どもたち/周りの人へのカミングアウト/LGBTQに対する理解/親の反応/親戚にカミングアウトするかどうか/パートナーシップと法整備と反LGBTの動き/仕事とセクシャリティ/最近の思い出/子どもたちはアライ 第3章 三〇代の女性二人で一歳の子どもを育てる〈かえでさん〉〈りつさん〉の話 二人の出会い/情報収集/「親戚のおじさん」的なドナーとの関係/妊娠期と出産/家族の状況/職場へのカミングアウト/子どもが生まれてから/望まれて生まれたことを伝えたい 第4章 二〇代の二人で0歳の子どもを育てる〈しおんさん〉〈ともえさん〉の話 二人の出会い/ドナー探し/カミングアウト/LGBTの認識/妊娠と出産/家族の役割/これからのこと/家族の関係性 エピローグ ルポ・さっぽろレインボープライド2022 「にじいろかぞく」とともに/パレードスタート/周りの人たち/パレードが終わって 解題 「聞き書き」を通じて見えてくるリプロダクティブ・ヘルス/ライツの問題 大島寿美子 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 遠藤あかり(えんどう・あかり) 2000年、北海道大空町生まれ。北星学園大学文学部心理・応用コミュニケーション学科卒業。本書は2022年度の卒業研究をもとにしたもの。 大島寿美子(おおしま・すみこ) 1964年、東京生まれ。北星学園大学文学部教授。著書に『がんの「語り」——語り手の養成から学校・医療・企業への派遣まで』(共著、寿郎社)、『「絆」を築くケア技法 ユマニチュード』(誠文堂新光社)、など。
MORE -

「銀河鉄道の夜」の謎を解く——〈彼ら〉はいったい何者なのか
¥1,980
国民的名作童話には《謎》がいっぱい。 賢治が遺した〈ことば〉を頼りにその謎解きに挑む《新感覚の文芸批評》! ●いじめられているジョバンニをカムパネルラはなぜ助けない? ●ジョバンニの父はなぜ監獄あに行った? ●沈没事故で死んだ姉弟はなぜ日本人なのか? ●「鳥捕り」が列車の乗り降り自由なのはなぜか? 「銀河鉄道の夜」を何度も読み返したくなる本。 三浦幸司 著 2022年3月刊 四六判/上製/184頁 本体1800円+税〔税込1980円〕 ISBN 978-4-909281-41-8 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 主な登場人物/物語のあらすじ 〔1〕ジョバンニはなぜ銀河鉄道に乗れたのか 第三次稿と第四次稿の違い ジョバンニと影との関わり ジョバンニの背負った苦難 父親が長期に不在(監獄にいるのかもしれない)とは カムパネルラの三度の沈黙 「ぼんやり」が意味するところ ジョバンニの上った「黒い丘」とは 「ケンタウル祭」はお盆――生と死がつながる行事 丘の上にある「天気輪の柱」とは何か ジョバンニはなぜ銀河鉄道に乗れたのか 〔2〕銀河鉄道は天空を走らない 銀河鉄道は空に昇らない 星と地上の一体化 空には星が残っていたのか 〔3〕「カトリック風の尼さん」とは何者か 銀河鉄道の様々な乗客たち 車内に現れた「尼さん」と「車室の中の旅人たち」 「尼さん」はジャンヌ・ダルクか 賢治の時代にジャンヌ・ダルクは聖人に 「ハルレヤ」を唱える人々 〔4〕「鳥を捕る人」の真実の姿 鳥獲りの容貌に注目しよう 鳥獲りは戦争の犠牲者 「ぼろぼろの外套」はアイデンティティー ほかにもある軍人のしるし 〔5〕「灯台守」とは何者か 「灯台守」は自立した労働者のこと 「灯台守」はなぜ「灯台守」なのか? 「灯台」=「時計台」という連想も 「灯台」は札幌の時計台だった? 〔6〕「姉弟」だけ日本人なのはなぜか 賢治の妹と弟がモデルの「姉弟」の登場 賢治はタイタニック号沈没事故を知っていたか 姉と弟だけなぜ日本人の名前なのか 「生き残った日本人」への非難 〔7〕「トウモロコシの種まきを語る人」とは何者か 声だけがする乗客 賢治が語った「アメリカンインデアンの式」 手塚治虫が捉えた「銀河鉄道の夜」の核心 〔8〕車窓から見える人たちについて 赤帽の信号手とはだれか 小さな小屋の前の子どもとは 空の工兵大隊の出現 シベリア出兵に向けた花巻での演習 双子の星の二つの話 「蝎の火」の物語 「ケンタウルの村」とは 赤い腕木を連ねて立つ二本の電信柱 〔9〕ジョバンニの友・カムパネルラのモデルとは 保阪説とトシ説 岩手山行の誓い 保阪嘉内の退学処分 「石炭袋」(そらの孔)と「きれいな野原」の意味 〔10〕カムパネルラとジョバンニにとっての「銀河鉄道」 カムパネルラの銀河鉄道 ジョバンニの銀河鉄道 ジョバンニの切符が意味するもの 「四つ折り」とは何を示すか 〔11〕銀河鉄道と路線についての不思議 銀河鉄道は軽便鉄道なのか 基本は銀河鉄道の位置関係の確定から 左岸を走る銀河鉄道とプリオシン海岸 〔12〕銀河鉄道の座席の位置 ボックスシートかロングシートか 乗客たちの座席の位置 右岸・左岸問題の解決 天の川銀河を見てみよう 終わりに——「銀河鉄道の夜」のテーマを考える 参考文献 あとがき —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 三浦幸司(みうら・こうじ) 1947年(昭和22年)、小樽市に生まれる。北大童話研究会、同人誌「原野の風」などに所属した。現在、日本児童文学者協会会員・評議員、北海道文学館理事、札幌市民芸術祭・市民文芸委員、子どもの本・九条の会会員、宮沢賢治学会イーハトーブセンター会員。札幌市在住。
MORE -

世界のひきこもり——地下茎コスモポリタニズムの出現
¥1,980
いじめ、うつ病、虐待、貧困……共通因子が見えてくる、ひきこもり歴35年の著者によるネットを通じた驚天動地の対話集。ひきこもりは日本特有の現象でも〈甘え〉によるものでもなかった!? 世界13カ国の当事者の声を聞け。 ぼそっと池井多 著 2020年10月刊 四六判/並製/288頁 本体1800円+税〔税込1980円〕 ISBN 978-4-909281-29-6 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 ●はじめに——地面を掘って国境を越える ●フランスのひきこもりギードの場合⋯⋯「ぼくは孤独が好きなんだ。パソコン、ベッド、安らぎがあれば十分さ。」 ●フランスのひきこもりテルリエンヌの場合⋯⋯「ひきこもりになんて、なりたくなかった。」 ●中国のひきこもり ●アメリカの元ひきこもりショーン・Cの場合⋯⋯「“伝統的な男性性”をぼくに期待するパパは敵だと思った。」 ●アレゼンチンのひきこもりマルコ・アントニオの場合⋯⋯「いじめる側を擁護する学校なんてごめんだ。」 ●インドのひきこもり ●インドの元ひきこもりニティンの場合⋯⋯「私たちは自分自身になるために少し時間が必要なだけなのです。」 ●イタリアの社会心理学者マルコ・クレパルディとの対話⋯⋯「彼らを助けたい、いや、『ぼくら』を助けたいのです。」 ●父との最後の電話 ●パナマ共和国のひきこもりヨスーの場合⋯⋯「ぼくはゴミだ。カスだ。負け犬だ。このままでは死んでしまう。」 ●フランスのひきこもりアエルの場合⋯⋯「ひきこもりになってぼくはようやく自分を生き始めた。」 ●スウェーデンのひきこもり ●バングラデシュのひきこもりイッポの場合⋯⋯「ぼくは自分で自分を部屋に監禁するようになったのさ。」 ●フィリピンのひきこもりCJの場合⋯⋯「日本のひきこもりはなんて恵まれているんだ!」 ●カメルーンの元ひきこもりアルメル・エトゥンディの場合⋯⋯「解決や成功を得る場所は、“社会”の中だけとは限らない。」 ●北朝鮮のひきこもり ●フランスのひきこもりジョセフィーヌの場合⋯⋯「醜くて、軽蔑に値して、病的であるのは社会の方よ。」 ●台湾の映画監督盧德昕との対話⋯⋯「ひきこもりにとって理想的な世界はどんなものですか。」 ●おわりに——ひきこもりのインタビュー論 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 ぼそっと池井多(ぼそっといけいだ) 1962年、横浜生まれ。東京都下在住。ひきこもり当事者や経験者の声を発信するメディア「ひきポス」の編集委員。 大学卒業を目前に控えた就職活動中にひきこもり始め、以後、形態をさまざまに変えながら断続的に35年ひきこもっている。 2017年、世界ひきこもり機構(GHO)を創設。近年は、長期化・高齢化したひきこもり当事者とともに、家族の語らいの場「ひ老会」や「ひきこもり親子公開討論」を主催している。
MORE -

だれも「おかしい」と言わない小学校〈超管理教育〉の実態
¥1,980
安倍政権下での“上意下達”の〈超管理教育〉の危うさを訴えるとともに〈学び〉の本質をさまざまな角度から掘り下げた、教師・保護者必読の書。 「これおかしくないですか?」 ●職員会議が、管理職からの指示をパソコンで伝える場となっている。 ●ほとんどの小学校教諭が「英語」を教える免許を持っていないのに、英語の授業をさせられている。 ●授業時間が詰まり過ぎていて、子どもたちは給食を15分で食べなければならない。 ●教員の仕事量は年々増え続けているのに、「働き方改革」で「残業するな」と管理職から言われる。そのために教員はみな家に仕事を持ち帰っている。 ……ほか。 平山裕人 著 2020年4月刊 四六判/並製/228頁 本体4500円+税〔税込4950円〕 ISBN 978-4-909281-28-9 C0037 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 第1章 四〇年で小学校教育はこんなに変わった 第2章 知られざる小学校の行事と驚きの教育内容 第3章 日本の教育史から「学び」を考える 第4章 ブラック化する現代教育 第5章 保護者に知っておいてもらいたいこと —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 1958年、北海道小樽市生まれ。北海道教育大学卒。1981年から小学校教員となり、北海道内の小学校数校に勤務したのち、2019年に“平教員”のまま定年退職。現在、小樽市の自宅でひっそりと私塾を経営。『シャクシャインの戦い』(寿郎社)、『アイヌ地域史資料集』『ワークブック アイヌ・北方領土学習にチャレンジ』『アイヌ語古語辞典』『アイヌの歴史——日本の先住民族を理解するための160語』(以上、明石書店)など著書多数。
MORE -

いわて星日和
¥1,870
ダウン症の娘とともに札幌から岩手県奥中山へ移り住んだ著者のイーハトヴな日々を綴った移住エッセイ。 有田美江 著 2017年8月刊 四六判/並製/272頁 本体1700円+税〔税込1870円〕 ISBN 978ー4ー909281ー04ー3 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 いわてに越して ショウガイジの母・初級 フキノトウのお味噌 シホの寮生活 南部の小絵馬 ねぶた祭りに出かけて 秋の藍染め 同窓会 温泉と星空と 友人と温泉と ネコマルと子猫たち 町内のカラオケ仲間 三春の滝桜 予防接種と母子手帳 新幹線が好き ふしぎな美容室 縄文公園祭り シホのパニック 二泊三日の黙想会 ハハ、トゲ刺さる 最強の火付け 集落のコンビニで冬 夏の暑さとちゃぶ台返し 沖縄旅行の思い出 ママ友、リヨコさん 思いがけないしあわせ マカオの座敷わらし 草刈りとシホの実習 シズクイシの桜 〈ゆりかごの巣〉 おばあさん わらび座を観て 盛岡の休日 賢治さんとアール・ブリュット 最後の春休み あとがき——ヤドリギ・ハハコ —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 有田美江(ありた・よしえ) 1954年北海道広尾町生まれ。藤女子短期大学国文科卒業。高校卒業まで北海道十勝地方の大樹町で育ち、その後2011年まで札幌市在住。 東日本大震災後、ダウン症の三女と共に岩手県一戸町東中山に移住。1994~2010年児童文学同人誌「まほうのえんぴつ」同人。2012年季刊詩誌『舟』(盛岡)同人となる。2004年小説「約束の町」(「まほうのえんぴつ」第23号)で第38回北海道新聞文学賞(創作・評論部門)を受賞。
MORE -

北の学芸員とっておきの《お宝ばなし》——北海道で残したいモノ伝えたいコト
¥1,650
全道各地の博物館・資料館の学芸員たちが“おらが町のちょっとイイ話”“自慢の所蔵品”について熱く語った1冊。北の自然と文化と人間にまつわる選りすぐりの49編を集めた“北海道ウンチク本”の決定版。 北海道博物館協会学芸職員部会 編 2016年11月刊 四六判/並製/360頁 本体1500円+税〔税込1650円〕 ISBN 978ー4ー902269ー92ー5 C0039 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第1章 謎を秘めた北海道の生き物たち 第2章 プレート衝突が生み出した大地に眠るもの 第3章 天空に広がる星と月 第4章 ワイズユース・自然と人間の関わり 第5章 大地が育む人のおおらかさ・あたたかさ 第6章 北の大地で活躍した人々 第7章 北海道の戦争の記憶 第8章 地域に残る先祖伝来の風習 第9章 アイヌ語地名とアイヌ文化の伝承 第10章 遺跡から見えてくる古代の文化・風習 第11章 まちの記憶と文化を刻む古い建物や資料 あとがきに代えて —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【編者略歴】 北海道博物館協会学芸職員部会 北海道内各地の博物館・美術館・動物園・水族館等に勤務する学芸員有志が集う専門職集団。 北海道博物館協会(1961年〜)に属し、研修活動の場を通じて学芸職員としてのスキルアップと情報共有に取り組むと共に、学芸員それぞれの専門分野を生かして博物館相互の交流・連携を推し進めている。 1977年の設立で2016年に40周年を迎えた。会員数は約180名。
MORE -

地域と演劇——弘前劇場の30年
¥1,870
現代演劇の雄「弘前劇場」。その劇作家・演出家の著者が、自身の高校演劇時代から、アングラ芝居を経て新しい表現に辿り着き、いまだ進化し続ける30年の日々と、地域で演劇を創る意味を初めて明かした1冊。 長谷川孝治 著 2008年10月刊 四六判/並製/224頁 本体1700円+税〔税込1870円〕 ISBN 978ー4ー902269ー31ー4 C0076 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 第1章 命名「弘前劇場」 第2章 稽古場を持つ 第3章 東京公演を打つ 第4章 新しい演劇の誕生 第5章 地域の演劇から、より開かれた世界へ 第6章 ドイツで得たもの 第7章 国際交流と青森県立美術館 第8章 生活の真ん中に演劇を置く —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 長谷川孝治(はせがわ・こうじ) 1956年(昭和31年)、青森県浪岡町(現青森市)生まれ。劇作家・演出家。青森県立美術館の舞台芸術総監督。78年、立正大学文学部哲学科在学中に、俳優の福士賢治、舞台監督の野村眞仁とともに青森県弘前市で「劇団弘前劇場」を旗揚げ。82年の大学卒業後は青森県で公立高校の教師をしながら演劇活動を続ける。95年、『職員室の午後』で第一回日本劇作家協会最優秀新人賞を受賞。2005年、ドイツ公演、2007年、韓国公演を成功させる。
MORE