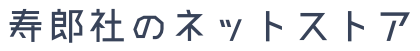-


石炭挽歌⸺NHK札幌放送局〈炭鉱事故〉担当アナウンサーの記録
¥2,530
昭和40年代⸺それは炭鉱事故が頻発し北海道から石炭が消えていった時代。美唄、赤平、夕張⸺炭鉱災害の現場で実況中継をしていた元NHKアナウンサーが記した当時の街と人と企業の姿。 末利光 著 2025年4月刊 四六判/上製/264頁 本体2300円+税〔税込2530円〕 ISBN 978-4-909281-69-2 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに プロローグ 第1章 美唄⸺一九六八年 第2章 赤平⸺一九六九年 第3章 赤平⸺一九七〇年 第4章 廃墟 第5章 事故の科学 第6章 落盤と山はね 第7章 北海道大学鉱山工学科 第8章 北炭夕張第二鉱と太平洋炭鉱の中へ⸺一九六七年 第9章 一九六五年の北炭ガス爆発事故の裁判記録から 第10章 石炭産業の衰退 第11章 石炭政策の失敗 第12章 生産性の優先 第13章 撤退 第14章 朝鮮人労働者と組夫 第15章 閉山 第16章 女性たち 第17章 再生の兆し⸺三菱大夕張炭鉱、一九七〇年 第18章 何でもやる 第19章 激動の昭和四七年⸺一九七二年 第20章 夕張、再び⸺一九八三年 あとがき⸺一九八三年 あとがきのあとがき⸺二〇二五年 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 末利光(すえ・としみつ) 1932年(昭和7年)、東京生まれ。早稲田大学文学部ドイツ文学科卒業。 1958年、NHKに入局、アナウンサーとなる。初任地である北海道帯広局の後、東京・札幌・甲府・仙台・岡山の各局に勤務。その間の1979年に、企画参加・出演・ナレーションを担当した短編映画『地方病との斗い』が第20回科学映画祭で科学技術長官賞受賞。1989年に講談師・二代目神田山陽より真打を許され「神田甲陽(かんだこうよう)」を名乗る。 1991年、甲府市長選出馬のためNHK退職。1995年より13年間、笛吹市春日居郷館・小川正子記念館館長を務め、現在は名誉館長。山梨県立女子短期大学、調布学園女子短期大学、ウィーン大学日本学研究所などで日本語表現と日本文化について講師を務める。2019年、2020年に長編舞台講談『武田勝頼の妻・花園』を東京と山梨で開催する。 著書に『甲州庶民伝 上・下』(NHK出版)〔テープ48巻の企画・編集・朗読を担当〕、『ことばのおへそ』『間の美学⸺日本的表現』(三省堂)、『クリーン選挙わたしの闘い』(講談社)、『ハンセン病報道は真実を伝え得たか』(JLM出版)、『コロナに翻弄された家』(毎日新聞社)、『信玄かるた(再販・信玄公かるた)』『昭和史かるた』(自費出版)など。
MORE -

芦別 炭鉱〈ヤマ〉とマチの社会史
¥4,400
芦別最後の坑内掘炭鉱の閉山(1992年三井芦別炭鉱閉山)から30年をへて明らかにされた〈炭鉱内部の仕事〉〈賃金〉〈労働者の移入・移出〉〈事故の発生状況〉、そして〈住まい〉や〈子どもの学校〉〈女性たちの活動〉……。炭都・芦別に移住し、働き、暮らし、そして去って行った膨大な人たちの足跡を追った、気鋭の研究者たちによる〈炭鉱研究〉〈地域史研究〉の比類なき一冊。 嶋﨑尚子・西城戸誠・長谷山隆博 編著 2023年12月刊 B5判/並製/340頁(口絵52頁) 本体4000円+税〔税込4400円〕 ISBN 978-4-909281-56-2 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに⋯⋯嶋﨑尚子 写真記録 昭和の芦別⋯⋯長谷山隆博 編 第1章 石炭と電力のマチ——国産エネルギー供給地としての芦別の歴史⋯⋯島西智輝 第2章 ビルド鉱三井芦別の人員確保と労働者の定着⋯⋯嶋﨑尚子 第3章 ビルド鉱の衰退と閉山——芦別を去る人・留まる人⋯⋯嶋﨑尚子 第4章 樺太引揚者の足跡から辿る戦後の芦別と石炭産業⋯⋯坂田勝彦 第5章 炭鉱の学校と子ども⋯⋯笠原良太 第6章 三井芦別炭鉱での仕事⋯⋯清水拓 第7章 災害報告から読む三井芦別炭鉱の事故⋯⋯長谷山隆博 第8章 三井芦別労働組合と精妙な賃金体系⋯⋯中澤秀雄 第9章 炭鉱町から地方都市へ——戦後芦別市の地域産業構造と社会移動の変遷……新藤慶 第10章 芦別で働いた人たち——芦別出身者と転入者の比較を通して⋯⋯新藤慶 第11章 芦別の女性たちの組織活動——主婦会・婦人会、生活学校を中心として⋯⋯西城戸誠 終章 炭鉱は芦別に何を残したのか——まとめにかえて⋯⋯西城戸誠 あとがき⋯⋯長谷山隆博 年表 索引 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【編著者略歴】 嶋﨑尚子(しまざき・なおこ)⋯⋯1963年、東京都生まれ。早稲田大学文学学術院教授。専攻はライフコース社会学、家族社会学。 西城戸誠(にしきど・まこと)⋯⋯1972年、埼玉県生まれ。早稲田大学文学学術院教授。専攻は環境社会学・地域社会学。 長谷山隆博(はせやま・たかひろ)⋯⋯1959年、北海道生まれ。1993年の星の降る里百年記念館開館から芦別市で学芸員として勤務、2020年に定年退職。現在、同館アドバイザー。専攻は日本考古学、北海道近現代史。 【著者略歴】 笠原良太(かさはら・りょうた)⋯⋯1990年、茨城県生まれ。実践女子大学生活科学部生活文化学科専任講師。専攻は家族社会学、ライフコース社会学。 坂田勝彦(さかた・かつひこ)⋯⋯1978年、千葉県生まれ。群馬大学情報学部教授。専攻は社会問題の社会学、生活史研究。 島西智輝(しまにし・ともき)⋯⋯1977年、北海道生まれ。立教大学経済学部教授。専攻は日本経済史・経営史。 清水拓(しみず・たく)⋯⋯1991年、長崎県生まれ。早稲田大学総合人文科学研究センター招聘研究員、法政大学大原社会問題研究所兼任研究員。専攻は産業・労働社会学。 新藤慶(しんどう・けい)⋯⋯1976年、千葉県生まれ。群馬大学共同教育学部准教授。専攻は地域社会学、教育社会学。 中澤秀雄(なかざわ・ひでお)⋯⋯1971年、東京都生まれ。上智大学総合人間科学部教授。専攻は地域社会学。
MORE -

海のアイヌの丸木舟——ラポロアイヌネイションの闘い
¥2,640
アイヌにとって川で捕るサケは、神の魚(カムイチェプ)であり主食(シエペ=本当の食べ物)であった。その川サケ漁を明治政府は一方的に禁じ、今日に至っている。先住権としての川サケ漁の権限を求めて丸木舟を作り、明治以来の日本の不正義に立ち向かうアイヌ民族団体の激動の日々と、先住権問題の核心を追った渾身のルポルタージュ! 青柳絵梨子 著 2023年6月刊 四六判/並製/360頁 本体2400円+税〔税込2640円〕 ISBN 978-4-909281-53-1 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに プロローグ 丸木舟の出航 丸木舟での川サケ漁/新しいサケを迎える儀式/伝統舞踊 ラポロアイヌネイションとは 第一章 カムイチェプ 1 丸木舟を作る 送り出しのカムイノミ/丸木を浮かべる/受け取りのカムイノミ/丸木舟作りと川サケ漁の復活/記紀に登場する「まつろわぬひとども」「蝦夷」/アイヌの信仰/アイヌとサケ資源/北海道旧土人保護法の制定/アイヌの人口調査/浦幌アイヌ協会の設立 2 米国のサーモンピープルから学ぶ 「あなたの物語を伝えなさい」/フィッシュウォーズの勃発/先住民は環境保護運動のリーダー/漁師の誇り/ダムを撤去させた一〇〇年の闘い/ダム撤去による生活の変化 3 コタンの再生に向けて 先住権の持ち主/複数形になっている権利行使の主体/サケ捕獲権確認訴訟のための勉強会/二風谷ダム訴訟/たった二人の反乱/文化享有権とは何か/国の反論/二風谷ダム訴訟の判決/司法が認めた「アイヌは先住民族」 第二章 ウポポイ vs 丸木舟 1 アイヌ新法が成立するまで 北海道ウタリ協会の陳情/「アイヌ民族に関する法律(案)」/紛糾した北海道アイヌ協会の再建総会/「アイヌ協会」から「ウタリ協会」への名称変更/法案作成のきっかけ/七〇年代前半の「ウタリ対策事業」構想/新法制定の検討と法案作成の動機/一九八四年「ウタリ問題懇話会」発足 2 先住権外し 舟にコタンコロカムイを描く/長根弘喜の意気込み/舟のひび割れ/サケ定置網漁の準備/「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」/二〇〇八年「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」設置/遺骨のDNA研究/土地・資源の「返還等ではなくて」/アイヌ施策推進法へ/ウポポイ構想の出現 3 ウポポイの開業と丸木舟の完成 ウポポイへ行ってみる/文様の揺らぎ/「仮に悲しい歴史があるとすれば」——文科相の発言/二〇二〇年七月、ウポポイ開業/「丸木舟、完成です!」/チプサンケ/丸木舟の着水/ラポロアイヌネイション誕生/ほんとにラポロでいいの? 第三章 墓標 1 アイヌ遺骨発掘の歴史 英国領事館員による幕末のアイヌ遺骨盗掘/外交問題に発展した遺骨盗掘事件/小金井良精の北海道発掘旅行/日本学術振興会の第八小委員会/児玉作左衛門の大量発掘/幕末に盗掘された遺骨を再び掘り出す/児玉作左衛門の「研究成果」/戦後も発掘を続ける/児玉コレクション 2 コタンへの返還と新たな問題の発生 再埋葬のカムイノミ/浦幌町の共同墓地への再埋葬/イチャルパ——先祖供養の儀式/闘いの始まり——海馬沢博の北大への質問状/北大の対応——ウタリ協会に限定して/「標本保存庫」としてのアイヌ納骨堂の完成/人骨台帳をめぐる小川隆吉の闘い/北大開示文書研究会の側面支援/小川・城野口らの提訴/小川・城野口に続く人々/北大との和解と「コタンの会」結成/白老の慰霊施設への遺骨集約は許さない 3 先住権の行使 遺骨返還を糸口に/浦幌アイヌ協会の意識の変化/丸木舟で初めてのサケを捕る/念願のアシリチェプノミ/サケの定置網漁/丸木舟作りという山を越えて/日本とアイヌのいびつな関係を正すラストチャンス エピローグ 新しい社会をめざして 「アイヌの美しき手仕事」展/伝統的サケ漁と訴訟のその後 関連年表 あとがき 参考文献・資料 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 青柳絵梨子(あおやぎ・えりこ) 1984年東京生まれ。大学卒業後、共同通信社に入社。大阪支社社会部、さいたま支局、東京エンタメ取材チームなどを経て、2013-2015年釧路支局、2015-2020年札幌支社に勤務(うち2年間休職してモスクワへ)。著書に、東京エンタメ取材チーム時代の新聞連載をまとめた『〈ルポ〉かわいい!——竹久夢二からキティちゃんまで』(寿郎社)がある。
MORE -

北海道大学発展の歴史とSDGs[エルムブックレット1]
¥1,100
国連SDGsに対する大学の社会貢献度が「国内第1位」「 世界第10位」(THEインパクトランキング2022)となった北大の〈力〉の源泉とそのさまざまな取り組みを解説 横田篤 著 2023年6月刊 A5判/並製/56頁 本体1000円+税〔税込1100円〕 ISBN 978-4-909281-51-7 C0030 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 第一章 SDGsに対する北海道大学の基本方針 はじめに 相互にリンクする一七の目標 大学に求められる姿 THEインパクトランキングの四つの指標と評価方法 土地や空間の利用法を定めたキャンパスマスタープラン サステイナビリティへの意識の高まり グリーン・スマート・サステイナブルキャンパス 大学としての明確なビジョン 第二章 SDGs達成に向けた具体的取り組み 新渡戸氏の意志を継いで SDGsを学ぶカリキュラム 2番「飢餓をゼロに」 14番「海の豊かさを守ろう」 15番「陸の豊かさも守ろう」 17番「パートナーシップで目標を達成しよう」 地球環境科学で気候変動に対策を 農林水産業で地域とともに 第三章 北海道大学を持続可能にする豊かな財産 自主・自立・独立のクラーク精神 独特な全人教育 “北大育ての親”佐藤昌介 アメリカ式の大学運営 日本の大学演習林の約六割を所有 演習林で資金を工面し総合大学へ おわりに——物的財産と知的財産の両輪で —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 横田篤(よこた・あつし) 1957年、東京都生まれ。1984年、北海道大学大学院農学研究科農芸化学科専攻博士後期課程修了(農学博士)後、味の素株式会社中央研究所勤務。1989年、農学部助手として北海道大学に戻り、2000年、大学院農学研究科教授となる。2015〜2019年、農学研究院長。2020年より北海道大学理事・副学長、サステイナビリティ推進機構SDGs事業推進本部長。
MORE -

〈聞き書き〉新しい家族のカタチ——子どもを迎える/育てる女性カップルたち[寿郎社ブックレット5]
¥1,210
政治家秘書によるLGBT差別発言、形ばかりで中身が伴わないパートナーシップ制度、出生数80万人割れの少子化……そのすべてに関わる子育てする女性カップルの〈表〉には出てこなかった〈生の声〉を伝える本。 遠藤あかり・大島寿美子 著 2023年3月刊 A5判/並製/112頁 本体1100円+税〔税込1210円〕 ISBN 978-4-909281-52-4 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 プロローグ 疑問の答えを見つけたくて 第1章 五〇代で女性パートナーとともに五歳の子どもを育てる〈まーりんさん〉の話 自分自身のセクシャリティ/パートナーとの出会い/シリンジ法で子どもを迎える/二人の人から精子提供を受けて/親戚として出産に立ち会う/子育て/子どもにどう伝えるか/二人の教育方針/五〇代——おばあちゃん世代の子育て/子育ての面白さ/法的に守られていない同性カップルの親子関係/周囲との関わり方/家族の証明——パートナーシップと公正証書/同性にも結婚の選択肢を/うちにパパはいない——子どもから見た家族/息子はおそらく出自のことで悩まない 第2章 四〇代で女性パートナーとともに二人の子どもを育てる〈マミーチャンヌさん〉の話 二〇代での結婚と離婚/今の家族になるまで/子どもたちへのカミングアウト/カミングアウトのきっかけ/子どもたちに受け入れてもらえるかどうか/うちはママが二人——パートナーと子どもたち/周りの人へのカミングアウト/LGBTQに対する理解/親の反応/親戚にカミングアウトするかどうか/パートナーシップと法整備と反LGBTの動き/仕事とセクシャリティ/最近の思い出/子どもたちはアライ 第3章 三〇代の女性二人で一歳の子どもを育てる〈かえでさん〉〈りつさん〉の話 二人の出会い/情報収集/「親戚のおじさん」的なドナーとの関係/妊娠期と出産/家族の状況/職場へのカミングアウト/子どもが生まれてから/望まれて生まれたことを伝えたい 第4章 二〇代の二人で0歳の子どもを育てる〈しおんさん〉〈ともえさん〉の話 二人の出会い/ドナー探し/カミングアウト/LGBTの認識/妊娠と出産/家族の役割/これからのこと/家族の関係性 エピローグ ルポ・さっぽろレインボープライド2022 「にじいろかぞく」とともに/パレードスタート/周りの人たち/パレードが終わって 解題 「聞き書き」を通じて見えてくるリプロダクティブ・ヘルス/ライツの問題 大島寿美子 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 遠藤あかり(えんどう・あかり) 2000年、北海道大空町生まれ。北星学園大学文学部心理・応用コミュニケーション学科卒業。本書は2022年度の卒業研究をもとにしたもの。 大島寿美子(おおしま・すみこ) 1964年、東京生まれ。北星学園大学文学部教授。著書に『がんの「語り」——語り手の養成から学校・医療・企業への派遣まで』(共著、寿郎社)、『「絆」を築くケア技法 ユマニチュード』(誠文堂新光社)、など。
MORE -

小さな労働組合 勝つためのコツ——攻める・守る・長く続ける
¥1,980
札幌地域労組の専従オルグ(指導者)として手がけた労働組合結成の数は日本一、労働運動に貢献した人に与えられる「山田精吾賞」(第1回)を現役で唯一受賞した《日本三大オルグ》の一人である著者が書いた、チョー分かりやすい〈労働組合の勝てる戦い方〉! 鈴木一 著 2022年10月刊 四六判/並製/224頁 本体1800円+税〔税込1980円〕 ISBN 978-4-909281-45-6 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第1章 労働相談——相手とケースを見極める 第2章 結成の準備から大会、使用者側への通知まで 第3章 不当労働行為——待ち遠しいと思えるように 第4章 団体交渉——ホンモノの労使対等を目指して 第5章 争議行為——“闘わずして勝つ”を最上として 第6章 救済申し立て——自分でできればさらに効果テキメン 第7章 弁護士にビビるな! 第8章 敵の中に味方をつくれ 第9章 個人加盟で闘う 第10章 外国人労働者からのSOS 第11章 内部告発——告発者の居場所と心を守る 第12章 労働相談に見る“名ばかり組合”の実態 第13章 組合運営と専従としての心構え おわりに —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 鈴木一(すずき・はじめ) 1954年、北海道札幌市生まれ。トラックとバスの運転手を経て、札幌地域労組専従。1990年から書記長を務め、定年を迎えた2014年より副委員長を務める。様々な技を駆使して労働相談を組合結成へとつなぎ、手掛けた組合結成数は日本のコミュニティユニオンの中で最多に達した。労働運動に貢献した人物に贈られる山田精吾賞の第1回を現職唯一で受賞し、「日本三大オルグ」の一人として現在も活動中。趣味は楽器演奏、鉄道旅行、映画鑑賞など。 〈新聞・雑誌等で紹介されています!〉 11月2日「朝日新聞」北海道版 インタビュー記事 11月8日「北海道新聞」道南版夕刊 大人のブックガイド 11月15日「財界さっぽろ」インサイドレポート 11月15日「北海道自治研」散射韻 11月30日「北海道新聞」北海道版 ひと2022 12月1日「労働法学研究会報」introduction 12月9日「北海道新聞」北海道版夕刊 コラム
MORE -

ふぞろいなキューリと地上の卵 ——〈無肥料・無農薬〉の野菜と卵を100キロ離れた札幌に宅配する北海道豊浦町の農家のおじさんのはなし
¥1,650
これがみんな喜ぶSDGsな農業だ! 海道豊浦町で始まった安全・安心でウマイ野菜と有精卵の農家自身による共同宅配サービス、そのノウハウとそれができるまでの涙と笑いのノンフィクション! 全国の小規模農家と〈SDGsな食と農〉を応援したい人たちの待望の一冊。 駒井一慶 著 2022年1月刊 四六判/並製/200頁 本体1500円+税〔税込1650円〕 ISBN 978-4-909281-36-4 C0061 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 プロローグ——消えたオスドリ 僕のセンス・オブ・ワンダー 木村秋則自然栽培農学校 ふぞろいなキューリ、真っすぐなキューリ 卵のないタマゴ屋さん 魔法の薬 鶏の餌 一個の角砂糖 一〇〇〇年の牛 野生の証明 ファーマーズシップ農業 僕の動的平衡 恋するタマゴ 牛乳の未来 食べる生命力 アイヌモシリ アクシデント再び 見える敵、見えない敵 新しい相棒 審判の日 持続可能農業への挑戦 エピローグ——オスドリが鳴いた 主な参考文献 あとがき —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 駒井一慶(こまい・いっけい) 1951年北海道豊浦町生まれ。酪農学園短期大学卒業後、家業の酪農業に従事する2000年に「こまい牧場の牛乳」の製造・販売を始めるも2007年に牧場・ミルクプラントを閉鎖。2008年から養鶏業を始め、有精卵『恋するタマゴ』を販売すると同時に、農家による共同宅配サービスも行う。現在、農業生産法人ドリームファーム・プロジェクト代表取締役。野菜宅配サービス「ふぞろいなキューリ・アソシエイツ」主宰。著書に『安全な卵の見分け方』『牛とキャッチボール』(共に中西出版〔電子出版〕)。「ふぞろいなキューリ」のウェブサイト:fuzoroinaqri.wixsite.com/home
MORE -
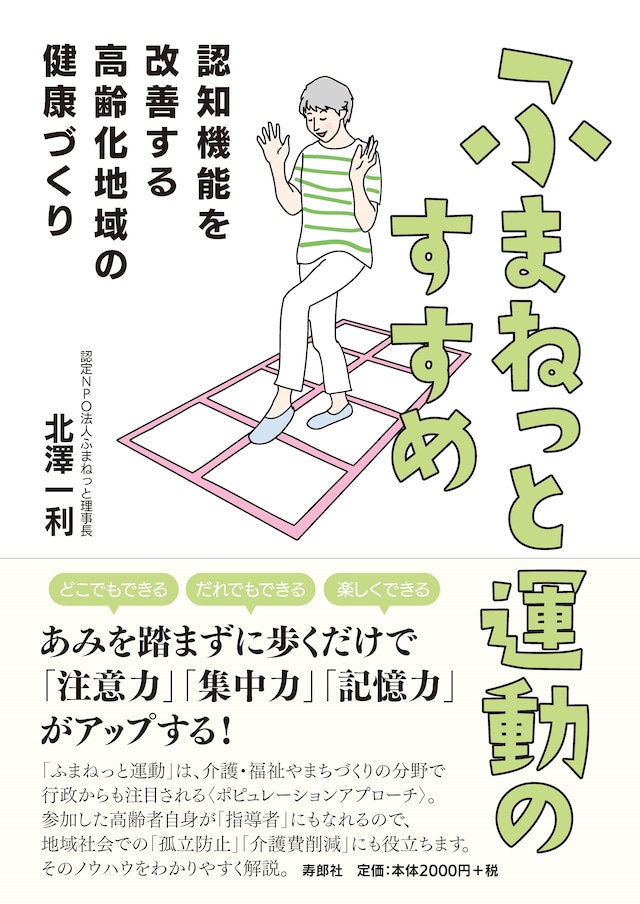
ふまねっと運動のすすめ——認知機能を改善する高齢化地域の健康づくり
¥2,200
あみを踏まずに歩くだけで高齢者の「注意力」「集中力」「記憶力」がアップする、ふまねっと運動。だれでもできる、どこでもできる、楽しくできる筋トレいらずの運動だから、いま、国が進める「ポピュレーションアプローチ」の実践例としても注目され、全国の介護施設や行政の健康づくり講座に広まっています。運動に参加した高齢者自身が「指導者」になれるのも大きな特長。地域社会での「認知症予防」「孤立防止」「介護費削減」にも役立つ、そのノウハウを本書でわかりやすく解説しています。 北澤一利 著 2021月5月刊 A5判/並製/204頁 本体2000円+税〔税込2200円〕 ISBN 978-4-909281-35-7 C0077 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第1章 ふまねっと運動の概要 第2章 歩行と認知機能を改善する理論と指導法 第3章 高齢者を指導者として養成する方法 第4章 市町村を支えるふまねっと運動の実績 第5章 住民主体の健康づくりで市町村が果たすべき役割 あとがき 参考文献 認定NPO法人ふまねっとから —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 北澤一利(きたざわ・かずとし) 1963年生まれ。静岡県出身。筑波大学体育専門学群卒業。同大大学院体育学研究科健康教育学専攻修了(体育学修士)。札幌医科大学大学院公衆衛生学講座修了(医学博士)。2004年、北海道教育大学教育学部釧路校助教授時代に学生とともに「ふまねっと運動」を開発。現在、認定NPO法人ふまねっと理事長。著書に『健康の日本史』(平凡社新書)、共著に『運動+(反)成長――身体医文化論Ⅱ』(慶応義塾大学出版会)、『健康ブームを読み解く』(青弓社)など。
MORE -

世界のひきこもり——地下茎コスモポリタニズムの出現
¥1,980
いじめ、うつ病、虐待、貧困……共通因子が見えてくる、ひきこもり歴35年の著者によるネットを通じた驚天動地の対話集。ひきこもりは日本特有の現象でも〈甘え〉によるものでもなかった!? 世界13カ国の当事者の声を聞け。 ぼそっと池井多 著 2020年10月刊 四六判/並製/288頁 本体1800円+税〔税込1980円〕 ISBN 978-4-909281-29-6 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 ●はじめに——地面を掘って国境を越える ●フランスのひきこもりギードの場合⋯⋯「ぼくは孤独が好きなんだ。パソコン、ベッド、安らぎがあれば十分さ。」 ●フランスのひきこもりテルリエンヌの場合⋯⋯「ひきこもりになんて、なりたくなかった。」 ●中国のひきこもり ●アメリカの元ひきこもりショーン・Cの場合⋯⋯「“伝統的な男性性”をぼくに期待するパパは敵だと思った。」 ●アレゼンチンのひきこもりマルコ・アントニオの場合⋯⋯「いじめる側を擁護する学校なんてごめんだ。」 ●インドのひきこもり ●インドの元ひきこもりニティンの場合⋯⋯「私たちは自分自身になるために少し時間が必要なだけなのです。」 ●イタリアの社会心理学者マルコ・クレパルディとの対話⋯⋯「彼らを助けたい、いや、『ぼくら』を助けたいのです。」 ●父との最後の電話 ●パナマ共和国のひきこもりヨスーの場合⋯⋯「ぼくはゴミだ。カスだ。負け犬だ。このままでは死んでしまう。」 ●フランスのひきこもりアエルの場合⋯⋯「ひきこもりになってぼくはようやく自分を生き始めた。」 ●スウェーデンのひきこもり ●バングラデシュのひきこもりイッポの場合⋯⋯「ぼくは自分で自分を部屋に監禁するようになったのさ。」 ●フィリピンのひきこもりCJの場合⋯⋯「日本のひきこもりはなんて恵まれているんだ!」 ●カメルーンの元ひきこもりアルメル・エトゥンディの場合⋯⋯「解決や成功を得る場所は、“社会”の中だけとは限らない。」 ●北朝鮮のひきこもり ●フランスのひきこもりジョセフィーヌの場合⋯⋯「醜くて、軽蔑に値して、病的であるのは社会の方よ。」 ●台湾の映画監督盧德昕との対話⋯⋯「ひきこもりにとって理想的な世界はどんなものですか。」 ●おわりに——ひきこもりのインタビュー論 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 ぼそっと池井多(ぼそっといけいだ) 1962年、横浜生まれ。東京都下在住。ひきこもり当事者や経験者の声を発信するメディア「ひきポス」の編集委員。 大学卒業を目前に控えた就職活動中にひきこもり始め、以後、形態をさまざまに変えながら断続的に35年ひきこもっている。 2017年、世界ひきこもり機構(GHO)を創設。近年は、長期化・高齢化したひきこもり当事者とともに、家族の語らいの場「ひ老会」や「ひきこもり親子公開討論」を主催している。
MORE -

いわて星日和
¥1,870
ダウン症の娘とともに札幌から岩手県奥中山へ移り住んだ著者のイーハトヴな日々を綴った移住エッセイ。 有田美江 著 2017年8月刊 四六判/並製/272頁 本体1700円+税〔税込1870円〕 ISBN 978ー4ー909281ー04ー3 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 いわてに越して ショウガイジの母・初級 フキノトウのお味噌 シホの寮生活 南部の小絵馬 ねぶた祭りに出かけて 秋の藍染め 同窓会 温泉と星空と 友人と温泉と ネコマルと子猫たち 町内のカラオケ仲間 三春の滝桜 予防接種と母子手帳 新幹線が好き ふしぎな美容室 縄文公園祭り シホのパニック 二泊三日の黙想会 ハハ、トゲ刺さる 最強の火付け 集落のコンビニで冬 夏の暑さとちゃぶ台返し 沖縄旅行の思い出 ママ友、リヨコさん 思いがけないしあわせ マカオの座敷わらし 草刈りとシホの実習 シズクイシの桜 〈ゆりかごの巣〉 おばあさん わらび座を観て 盛岡の休日 賢治さんとアール・ブリュット 最後の春休み あとがき——ヤドリギ・ハハコ —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 有田美江(ありた・よしえ) 1954年北海道広尾町生まれ。藤女子短期大学国文科卒業。高校卒業まで北海道十勝地方の大樹町で育ち、その後2011年まで札幌市在住。 東日本大震災後、ダウン症の三女と共に岩手県一戸町東中山に移住。1994~2010年児童文学同人誌「まほうのえんぴつ」同人。2012年季刊詩誌『舟』(盛岡)同人となる。2004年小説「約束の町」(「まほうのえんぴつ」第23号)で第38回北海道新聞文学賞(創作・評論部門)を受賞。
MORE -
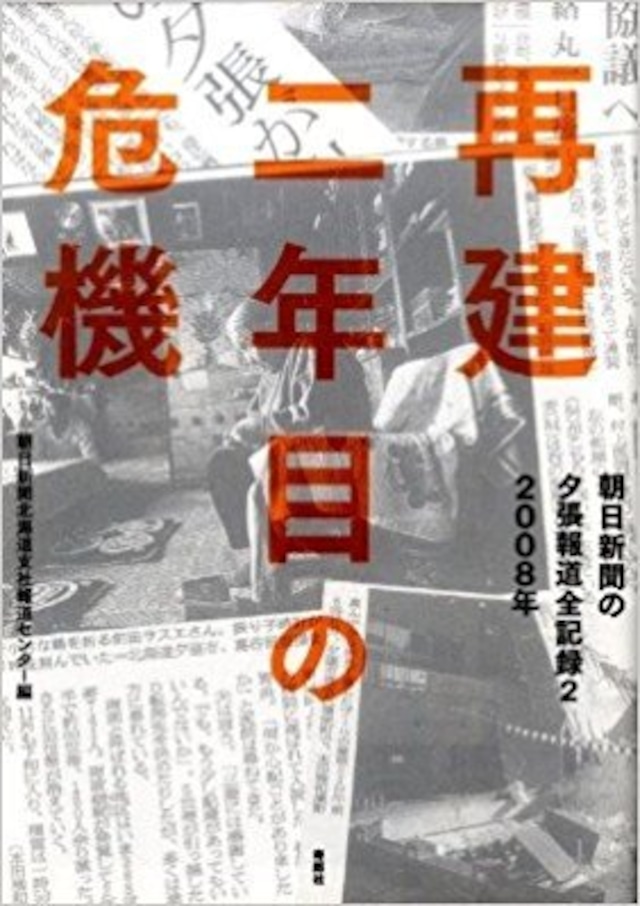
朝日新聞の夕張報道全記録2——再建二年目の危機
¥2,420
街が倒産すると何がいったいどうなるのか? 大型企画記事からや社説、天声人語、小さなベタ記事に至るまで、未曾有の一年を追った記者たちのすべての記事を完全網羅したシリーズ第二弾。 朝日新聞北海道支社報道センター 編 2009年8月刊 A5判/並製/296頁 本体2200円+税〔税込2420円〕 ISBN 978ー4ー902269ー34ー5 C0002 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 1月 人口、急速に減少 2月 加森観光、二施設返上 3月 市民プールの屋根、崩落 4月 消えゆく母校 5月 医療センターが経営危機 6月 病休相次ぐ市職員 7月 市長、「ふるさと納税」PR 8月 野ざらしの観光施設 9月 四度目の再建計画変更案 10月 夕張リゾート、指定管理をさらに返上 11月 市税・家賃などの滞納7億円 12月 年末の解雇通知 あとがき 人名索引
MORE -

農村へ出かけよう——農都共生と食育のすすめ
¥1,100
ストレスを吹き飛ばし、おいしく健康的な生活を送るための第一歩。それは農村へ足を運ぶこと。すべての答えはそこにある——。北海道おすすめの体験農場、牧場、農家レストラン、農家民宿、ワイナリーなどの情報も満載。 林美香子 著 2009年6月刊 四六判/並製/180頁 本体1000円+税〔税込1100円〕 ISBN 978ー4ー902269ー35ー2 C0061 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第Ⅰ部 農村へ出かけよう 第Ⅱ部 地産地消と食育のすすめ 第Ⅲ部 フランスから学ぶ農都共生 第Ⅳ部 地域の宝を見直そう 第Ⅴ部 農都共生フォーラムから あとがき 北海道のおすすめ農村スポット —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 林美香子(はやし・みかこ) 1976年北海道大学農学部卒業。札幌テレビ放送(STV)勤務をへて85年よりフリーのキャスター、農業ジャーナリスト。2006年、「農村と都市の共生による地域再生の基盤条件の研究」で北海道大学より博士(工学)取得。2008~2020年、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特任教授。北海道大学農学部客員教授。
MORE -

地域と演劇——弘前劇場の30年
¥1,870
現代演劇の雄「弘前劇場」。その劇作家・演出家の著者が、自身の高校演劇時代から、アングラ芝居を経て新しい表現に辿り着き、いまだ進化し続ける30年の日々と、地域で演劇を創る意味を初めて明かした1冊。 長谷川孝治 著 2008年10月刊 四六判/並製/224頁 本体1700円+税〔税込1870円〕 ISBN 978ー4ー902269ー31ー4 C0076 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 第1章 命名「弘前劇場」 第2章 稽古場を持つ 第3章 東京公演を打つ 第4章 新しい演劇の誕生 第5章 地域の演劇から、より開かれた世界へ 第6章 ドイツで得たもの 第7章 国際交流と青森県立美術館 第8章 生活の真ん中に演劇を置く —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 長谷川孝治(はせがわ・こうじ) 1956年(昭和31年)、青森県浪岡町(現青森市)生まれ。劇作家・演出家。青森県立美術館の舞台芸術総監督。78年、立正大学文学部哲学科在学中に、俳優の福士賢治、舞台監督の野村眞仁とともに青森県弘前市で「劇団弘前劇場」を旗揚げ。82年の大学卒業後は青森県で公立高校の教師をしながら演劇活動を続ける。95年、『職員室の午後』で第一回日本劇作家協会最優秀新人賞を受賞。2005年、ドイツ公演、2007年、韓国公演を成功させる。
MORE -

朝日新聞の夕張報道全記録1——崩落。それでも生きてゆく
¥3,520
街が倒産すると何がいったいどうなるのか? 大型企画記事からや社説、天声人語、小さなベタ記事に至るまで、未曾有の一年を追った記者たちのすべての記事を完全網羅したシリーズ第一弾。 朝日新聞北海道支社報道センター 編 2008年6月刊 A5判/並製/448頁 本体3200円+税〔税込3520円〕 ISBN 978ー4ー902269ー26ー0 C0002 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 1月 「再建元年」スタート 2月 住民、不安の声やまず 3月 財政再建団体に 4月 新市長に藤倉氏 5月 動けぬ夕張 6月 財政破綻を反面教師に 7月 止まらぬ職員流出 8月 小学校1校化へ 9月 再建計画変更案を提出 10月 売れるものなら何でも 11月 職員、さらに退職 12月 行政がマヒ寸前
MORE