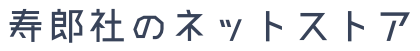-

北海道大学発展の歴史とSDGs[エルムブックレット1]
¥1,100
国連SDGsに対する大学の社会貢献度が「国内第1位」「 世界第10位」(THEインパクトランキング2022)となった北大の〈力〉の源泉とそのさまざまな取り組みを解説 横田篤 著 2023年6月刊 A5判/並製/56頁 本体1000円+税〔税込1100円〕 ISBN 978-4-909281-51-7 C0030 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 第一章 SDGsに対する北海道大学の基本方針 はじめに 相互にリンクする一七の目標 大学に求められる姿 THEインパクトランキングの四つの指標と評価方法 土地や空間の利用法を定めたキャンパスマスタープラン サステイナビリティへの意識の高まり グリーン・スマート・サステイナブルキャンパス 大学としての明確なビジョン 第二章 SDGs達成に向けた具体的取り組み 新渡戸氏の意志を継いで SDGsを学ぶカリキュラム 2番「飢餓をゼロに」 14番「海の豊かさを守ろう」 15番「陸の豊かさも守ろう」 17番「パートナーシップで目標を達成しよう」 地球環境科学で気候変動に対策を 農林水産業で地域とともに 第三章 北海道大学を持続可能にする豊かな財産 自主・自立・独立のクラーク精神 独特な全人教育 “北大育ての親”佐藤昌介 アメリカ式の大学運営 日本の大学演習林の約六割を所有 演習林で資金を工面し総合大学へ おわりに——物的財産と知的財産の両輪で —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 横田篤(よこた・あつし) 1957年、東京都生まれ。1984年、北海道大学大学院農学研究科農芸化学科専攻博士後期課程修了(農学博士)後、味の素株式会社中央研究所勤務。1989年、農学部助手として北海道大学に戻り、2000年、大学院農学研究科教授となる。2015〜2019年、農学研究院長。2020年より北海道大学理事・副学長、サステイナビリティ推進機構SDGs事業推進本部長。
MORE -

ふぞろいなキューリと地上の卵 ——〈無肥料・無農薬〉の野菜と卵を100キロ離れた札幌に宅配する北海道豊浦町の農家のおじさんのはなし
¥1,650
これがみんな喜ぶSDGsな農業だ! 海道豊浦町で始まった安全・安心でウマイ野菜と有精卵の農家自身による共同宅配サービス、そのノウハウとそれができるまでの涙と笑いのノンフィクション! 全国の小規模農家と〈SDGsな食と農〉を応援したい人たちの待望の一冊。 駒井一慶 著 2022年1月刊 四六判/並製/200頁 本体1500円+税〔税込1650円〕 ISBN 978-4-909281-36-4 C0061 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 プロローグ——消えたオスドリ 僕のセンス・オブ・ワンダー 木村秋則自然栽培農学校 ふぞろいなキューリ、真っすぐなキューリ 卵のないタマゴ屋さん 魔法の薬 鶏の餌 一個の角砂糖 一〇〇〇年の牛 野生の証明 ファーマーズシップ農業 僕の動的平衡 恋するタマゴ 牛乳の未来 食べる生命力 アイヌモシリ アクシデント再び 見える敵、見えない敵 新しい相棒 審判の日 持続可能農業への挑戦 エピローグ——オスドリが鳴いた 主な参考文献 あとがき —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 駒井一慶(こまい・いっけい) 1951年北海道豊浦町生まれ。酪農学園短期大学卒業後、家業の酪農業に従事する2000年に「こまい牧場の牛乳」の製造・販売を始めるも2007年に牧場・ミルクプラントを閉鎖。2008年から養鶏業を始め、有精卵『恋するタマゴ』を販売すると同時に、農家による共同宅配サービスも行う。現在、農業生産法人ドリームファーム・プロジェクト代表取締役。野菜宅配サービス「ふぞろいなキューリ・アソシエイツ」主宰。著書に『安全な卵の見分け方』『牛とキャッチボール』(共に中西出版〔電子出版〕)。「ふぞろいなキューリ」のウェブサイト:fuzoroinaqri.wixsite.com/home
MORE -

廃材もらって小屋でもつくるか——電力は太陽と風から
¥2,200
あこがれの富良野に五郎さん家風の小屋を20日で建てて暮らす—— 環境にも懐にもやさしい大人の秘密基地のつくり方ガイド。 イマイカツミ・川邉もへじ・家次敬介 著 2018年6月刊 A5判/コデックス装/168頁 本体2000円+税〔税込2200円〕 ISBN 978-4-909281-11-1 C0077 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 0日目 心と材の準備をするの巻 1日目 イメージを膨らませるの巻 2日目 基礎をつくるの巻 3日目 躯体を組むの巻 4日目 屋根の骨組みをつくるの巻 5日目 屋根にトタンを張るの巻 6日目 小屋の細部を決めるの巻 7日目 窓と扉を付けてみるの巻 8日目 床をつくるの巻 9日目 防水シートを張るの巻 10日目 新しいアイデアを加えるの巻 11日目 小屋を暖かくするの巻 12日目 ウッドデッキをつくるの巻 13日目 電気のことを考えるの巻 14日目 太陽光パネルを取り付けるの巻 15日目 内壁を張るの巻 16日目 けがをするの巻 17日目 畳を注文するの巻 18日目 入口の造作に頭をひねるの巻 19日目 小屋の魅力を高めるの巻 20日目 ガラスと畳が入って完成!の巻 小屋を楽しむ おわりに —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 イマイカツミ(今井克) 1975年大阪府生まれ、横浜市育ち。成蹊大学文学部卒。出版社に勤務したのち退社して画業に専念。2001年、富良野市に移住し、農作業ヘルパーなどをしながら、北海道や国内外の風景を描き続ける。著書に『大人が楽しむはじめての塗り絵 北海道の旅』(いかだ社)、『大地のうた富良野』『北海道の駅舎』(いずれもイマイカツミ探訪画集、寿郎社)など。 川邉もへじ(かわなべ・もへじ) 1969年熊本県生まれ。ログハウス制作、工務店での仕事を経て、現在は南富良野町で大工兼木工作家。「cafe ゴリョウ」(富良野市)、「フォーチュンベーグルズ」、「ちっちゃなちっちゃなギャラリー珈琲ゆっくりYuku」(いずれも南富良野町)、などのリノベーションを手がけている。 家次敬介(いえつぐ・けいすけ) 1965年北海道中標津町生まれ。富良野高校卒。家電店勤務を経て独立し、現在は富良野市で「環境にやさしい電器店 有限会社三素」を経営。日夜、エコ製品の家庭への普及をめざし奔走している。
MORE -

草地と語る——〈マイペース酪農〉ことはじめ
¥2,750
自然に則った酪農経営がNHK「プロフェッショナル仕事の流儀」で紹介され、全国的に知られることとなった北海道中標津町の酪農家・三友盛行さんの〈マイペース酪農〉。その考え方と実践法を最新データからわかりやすく解説した注目のテキスト。化学肥料と濃厚飼料を減らせば土・草・牛が蘇る! 近代日本の酪農のあり方を問い直し、三友農場の循環型酪農を解析する。 佐々木章晴 著 2017年3月刊 四六判/上製/248頁 本体2500円+税〔税込2750円〕 ISBN 978ー4ー902269ー97ー0 C0061 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 まえがき 第一章 草地に立つ 第二章 歴史を振り返る 第三章 風土は劇的に変わった 第四章 農学・農業技術は役に立つか 第五章 主体的に生きることと技術 第六章 マイペース酪農への気づき 第七章 三友農場の「一ha1一頭」の合理性 第八章 カギを握る「アルミニウム」 第九章 春施肥の意味 第一〇章 遅刈り、しかし適期刈り 第一一章 腐植、そして腐植酸 第一二章 永年草地を中心に回る経営 あとがき 主な参考文献 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 佐々木章晴(ささき・あきはる) 1971年、北海道別海町生まれ。12歳まで根釧地方で育つ。1995年、帯広畜産大学畜産環境科学専攻修了。専門は集約放牧による乳牛飼育技術に関する研究。95年4月より農業教員として主に栽培環境を担当し富良野農業高校・中標津農業高校などに勤務。2001年より〈マイペース酪農〉のモデルとされる三友農場の調査研究を行なう。2007年4月より当別高校園芸デザイン科教諭。著書に『これからの酪農経営と草地管理』(農文協)がある。
MORE -
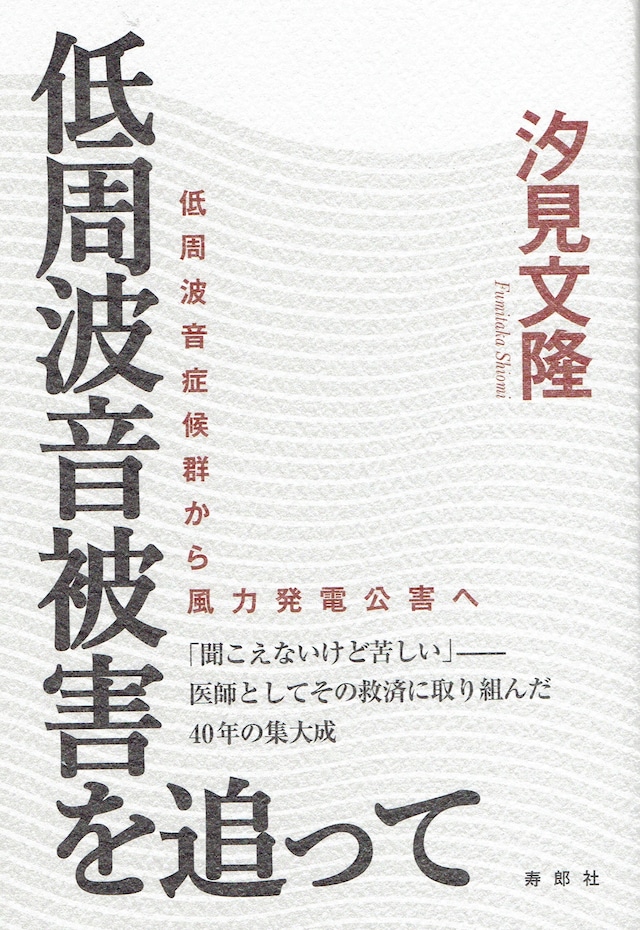
低周波音被害を追って——低周波音症候群から風力発電公害へ
¥2,090
低周波音被害とは人間の耳には聞こえない低周波の空気振動が頭痛・吐き気・呼吸困難・しびれ等を引き起こす健康被害のこと。「聞こえないけど苦しい」と訴える被害者の救済に取り組んだ著者の40年の集大成。今後、より大きな問題となっていくであろう”知られざる公害”について書かれた衝撃の一冊。 汐見文隆 著 2016年10月刊 四六判/上製/240頁 本体1900円+税〔税込2090円〕 ISBN 978ー4ー902269ー94ー9 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 まえがき 序章 第1章 低周波音症候群——無視され続ける被害者たち 1 因果律の世界 2 メリヤス工場隣家の被害——最初の低周波音被害経験例 3 聴覚と左脳(言語脳) 4 大阪府八尾市・綿実油工場——私の次なる経験例 5 気導音と骨導音 6 低周波音被害——これでもまだ騒音被害と混同するのか 7 低周波音被害者は聴覚が鈍いのか? 8 低周波音被害のその後の姿とエコキュート 9 むすび 第2章 風力発電公害——超低周波空気振動症候群(風車病) 1 風力発電機の住民被害は低周波音被害では? 2 愛知県田原市・久美原風力発電所——どちらが悪い? 3 愛媛県伊方町・佐田岬半島——悲しい風車の一列縦隊 4 静岡県東伊豆町奈良本——住民の建築と幸福の破壊 5 むすび おわりに 追記 冤罪を問う —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 汐見文隆(しおみ・ふみたか) 1924年(大正13年)京都市生まれ。京都帝国大学医学部卒業後、内科医となる。和歌山赤十字病院第一内科部長を経て1965年和歌山市内で汐見内科を開業。和歌山県保険医協会理事(公害担当)、全国保険医団体連合会の公害環境対策部員を務めたほか、1972年より「和歌山から公害をなくす市民のつどい」の代表世話人となり、市民による公害問題の学習の場としての「公害教室」を31年間(166回)開催。1995年、低周波音公害の調査や公害被害者の救済活動で第4回田尻賞を受賞。 2016年3月20日、逝去。享年92。本書は遺稿。
MORE -

泊原発とがん[寿郎社ブックレット1]
¥770
著者・斎藤武一が保健所で偶然手に入れた資料『北海道における主要死因の概要』——。その統計資料によると、泊原発が稼働してから【がん死亡比】がナンバー1の道内市町村は「泊村」であるという。2位は対岸にある「岩内町」、3位も近郊の「寿都町」……。事故が起きなくても放射性物質を出し続ける原子力発電所。泊原発の放射性物質は、風に乗り、雨に混じり、北海道各地に降り注いでいるのではないか!?〈泊原発とがん〉の関係について論じた衝撃のリポート。 斎藤武一 著 2016年10月刊 A5判/並製/86頁 本体700円+税〔税込770円〕 ISBN 978ー4ー902269ー87ー1 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 第Ⅰ部 泊原発周辺で〈がんの過剰死〉が起きている 1 〈泊原発とがん〉を調べるきっかけ 2 資料を読み解きわかった衝撃の事実 3 内陸より〈がん死〉が多い海沿いの町 第Ⅱ部 なぜ内陸部で〈乳がん死〉が増えているのか? 1 泊原発と〈乳がん死〉の関係について 2 泊原発が運転する前と運転した後の変化 3 札幌など五大都市の〈乳がん死〉 4 [追論]泊原発周辺のがん多発のさらなる要因について [巻末資料] —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 斎藤武一(さいとう・たけいち) 1953年、北海道岩内町生まれ。岩内町職員(保育士)を経て現在岩内町で学主塾を経営。市民団体「岩内原発問題研究会」代表。「泊原発の廃炉を求める訴訟」原告団長。「原子炉メーカーを糾弾する会」副代表。 泊原発から出る温排水の影響を調べるため1978年、25歳のときから岩内港の防波堤で水温観測を開始し、2016年現在も継続中。泊村の泊原発から海を挟んで6キロほどの距離にある地元岩内町で原発に反対し続ける。 著書に『【原発紙芝居】子どもたちの未来のために——とても悲しいけれど空から灰がふってくる』(寿郎社、2013年)、『海の声を聞く——原子力発電所温排水の観測25年』(七つ森書館、2003年)、『木田金次郎 山ハ空ヘモレアガル』(北海道新聞社、2007年)、『理想の保育園——障がい児は神様』(文芸社、2009年)がある。
MORE -

大間原発と日本の未来
¥2,090
プルトニウムを消費するために下北半島に建設されている世界初のフルMOX原発〈大間原発〉。対岸の函館市でその建設反対運動にかかわってきた著者が”世界一危険な原発”大間原発の実相を自身の体験と地元の人々の言葉から描いた。日本のいまと未来を考えるための〈辺境〉からの現場報告。 野村保子 著 2015年3月刊 四六判/並製/296頁 本体1900円+税〔税込2090円〕 ISBN 978ー4ー902269ー76ー5 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 序章 豊かな海にあらわれた〈怪物〉 第1章 大間町訪問——二〇一二年八月 第2章 危険な原発を受け入れたまち 第3章 大間町で反対する人——熊谷あさ子さんの闘い 第4章 大間町で反対する人々——市民グループと漁師たちの闘い 第5章 対岸のまち函館の反対運動——〈ストップ大間原発道南の会〉ができるまで 第6章 裁判にいたる道 第7章 フルMOX原発の危険性 第8章 改良型沸騰水型軽水炉ABWRとは何か 第9章 危険な実験——初めてづくしの大間原発 第10章 なぜ大間町だったのか——“犠牲”となる下北半島 第11章 函館の反原発運動の広がり 第12章 大間原発の未来の姿 第13章 変わる大間町 終章 地方自治体が原発を止める——函館市の挑戦 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 野村保子(のむら・やすこ) 北海道函館市生まれ。フリーライター。1980年代から無農薬野菜の共同購入グループに参加。1994年から反原発運動にかかわる。著書に『原発に反対しながら研究を続ける小出裕章さんのおはなし』(クレヨンブックス)がある。
MORE -

〈ルポ〉原発はやめられる——ドイツと日本
¥1,870
第27回地方出版文化功労賞功労賞奨励賞受賞。 ドイツ社会の〈哲学〉とエネルギー転換の現場、そして福島の現実を詳細に取材して、原発の”なし崩し的再稼働”に走る日本社会に警鐘を鳴らす。 小坂洋右 著 2013年8月刊 四六判/並製/240頁 本体1700円+税〔税込1870円〕 ISBN 978ー4ー902269ー61ー1 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 序章 一九九二年、ベラルーシにて 第1章 倫理委員会で決めたドイツの脱原発 第2章 社会学者を訪ねてドイツへ 第3章 科学文明のリスク―チェルノブイリの教訓 第4章 福島第一原発という人災事故 第5章 モラルが崩壊する時 第6章 未来へのツケ 第7章 ドイツ・エネルギー転換の現場 第8章 熱い住民運動、中立の専門家 第9章 福島——コミュニティーの分断と生命圏の痛み 第10章 日本の進むべき道 終章 前福島県知事・佐藤栄佐久さんとの対話 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 小坂洋右(こさか・ようすけ) 1961年(昭和36年)札幌市生まれ。北海道大学文学部卒。英オックスフォード大学ロイター・ファウンデーション・ジャーナリスト・プログラム修了。アイヌ民族博物館学芸員などを経て北海道新聞記者に。北海道庁公費乱用取材班として新聞協会賞、日本ジャーナリスト会議(JCJ)奨励賞を受賞。
MORE -

【原発紙芝居】子どもたちの未来のために——とても悲しいけれど空から灰がふってくる
¥1,650
北海道岩内町で〈泊原発〉の温排水を35年以上測り続ける元・町職員の著者が、原発と放射能の怖さをわかりやすく「故郷の海を守りたい」「とても悲しいけれど空から灰がふってくる」の二話にまとめた紙芝居(絵本)。一時間余りの実演DVD付き。 斎藤武一 著 2013年4月刊 A5変型判/並製/96頁 本体1500円+税〔税込1650円〕 ISBN 978ー4ー902269ー59ー8 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 故郷の海を守りたい とても悲しいけれど空から灰がふってくる あとがき —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 斎藤武一(さいとう・たけいち) 1953年、北海道岩内町生まれ。岩内町職員(保育士)を経て現在岩内町で学主塾を経営。市民団体「岩内原発問題研究会」代表。「泊原発の廃炉を求める訴訟」原告団長。「原子炉メーカーを糾弾する会」副代表。 泊原発から出る温排水の影響を調べるため1978年、25歳のときから岩内港の防波堤で水温観測を開始し、2016年現在も継続中。泊村の泊原発から海を挟んで6キロほどの距離にある地元岩内町で原発に反対し続ける。 著書に『海の声を聞く——原子力発電所温排水の観測25年』(七つ森書館、2003年)、『木田金次郎 山ハ空ヘモレアガル』(北海道新聞社、2007年)、『理想の保育園——障がい児は神様』(文芸社、2009年)がある。
MORE -

北海道電力〈泊原発〉の問題は何か
¥1,760
〈泊原発〉が事故を起こせば、西風にのって放射能は全道に拡がり「日本の食糧基地」は壊滅する。立地の地形・構造上の弱点・倫理と法の問題・稼働の意味など、各分野の専門家がその危険性を指摘した〈泊原発〉に関する唯一の本。 泊原発の廃炉をめざす会 編 2012年11月刊 四六判/並製/263頁 本体1600円+税〔税込1760円〕 ISBN 978-4-902269-55-0 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 第1章 日本を変えるステージの始まり 第2章 倫理から見た原発 第3章 泊原発に迫る地震と津波の危険 第4章 泊原発は構造的にどこが危険なのか 第5章 フクシマで起きたことが泊で起こったら 第6章 原発なしでも北海道はやっていける 第7章 司法は福島事故に重い責任がある —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【編者略歴】 泊原発の廃炉をめざす会 2011年7月7日に設立された市民団体。「泊原発の廃炉を求める訴訟」の原告団、弁護士を支援するとともに、函館市や北海道全体に大きな危険をもたらす大間原発の建設に反対している。
MORE -

農村へ出かけよう——農都共生と食育のすすめ
¥1,100
ストレスを吹き飛ばし、おいしく健康的な生活を送るための第一歩。それは農村へ足を運ぶこと。すべての答えはそこにある——。北海道おすすめの体験農場、牧場、農家レストラン、農家民宿、ワイナリーなどの情報も満載。 林美香子 著 2009年6月刊 四六判/並製/180頁 本体1000円+税〔税込1100円〕 ISBN 978ー4ー902269ー35ー2 C0061 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第Ⅰ部 農村へ出かけよう 第Ⅱ部 地産地消と食育のすすめ 第Ⅲ部 フランスから学ぶ農都共生 第Ⅳ部 地域の宝を見直そう 第Ⅴ部 農都共生フォーラムから あとがき 北海道のおすすめ農村スポット —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 林美香子(はやし・みかこ) 1976年北海道大学農学部卒業。札幌テレビ放送(STV)勤務をへて85年よりフリーのキャスター、農業ジャーナリスト。2006年、「農村と都市の共生による地域再生の基盤条件の研究」で北海道大学より博士(工学)取得。2008~2020年、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特任教授。北海道大学農学部客員教授。
MORE