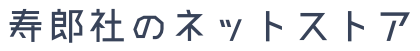-


近現代アイヌ文学史論⸺アイヌ民族による日本語文学の軌跡〈現代編〉
¥3,190
絶えまない逆境を乗り越えて、発展を遂げてきた現代アイヌ文学。その戦後から今日までの軌跡に光を当てる。 小説、評論、エッセイ、詩歌、自伝、新聞、雑誌、同人誌⸺〈近代編〉と併せて1000頁を超える在野研究の金字塔、完結。 須田茂 著 2025年9月刊 四六判/並製/564頁 本体2900円+税〔税込3190円〕 ISBN 978-4-909281-68-5 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第1章 戦後のアイヌ文学の幕開け⸺言論活動の復活 一節 高橋真と『アイヌ新聞』の挑戦 二節 『北の光』と新生北海道アイヌ協会 三節 進駐軍とアイヌ民族の言論活動 第2章 知里真志保の業績と影響 一節 知里真志保の「アイヌ系日本人」論 二節 アイヌの人たちの知里真志保像 三節 知里真志保と近現代アイヌ文学 四節 現代アイヌ文学への貢献 第3章 現代小説の台頭 一節 鳩沢佐美夫(1935〜1971) 二節 上西晴治(1925〜2009) 三節 鳩沢佐美夫と上西晴治の交錯 第4章 1970年代のアイヌ文学の展開 一節 「対談 アイヌ」以後の『日高文芸』 二節 「葦の会」と『葦の会だより』 三節 新聞『アヌタリアイヌ⸺われら人間』 四節 佐々木昌雄の仕事 五節 1970年代のアイヌ著述家群像 六節 同人誌『北方群』 第5章 脱植民地化への挑戦 一節 結城庄司(1938〜1983) 二節 荒井源次郎(1900〜1991) 三節 海馬沢博(1919〜1987) 第6章 「エカシ」たちの復活とその仕事 一節 森竹竹市・貫塩喜蔵の復活 二節 山本多助(1904〜1993) 三節 貝澤正(1912〜1992) 四節 葛野辰次郎(1910〜2002) 第7章 337 萱野茂の仕事 第8章 351 アイヌ民族による現代詩歌 一節 現代詩 二節 短歌 三節 俳句 第9章 多様化する現代アイヌ文学 一節 自伝文学の活性化 二節 児童文学の広がり⸺絵本と童話 三節 1980年代以降の主なアイヌ文学の著作 第10章 現代アイヌ文学についての試論 一節 現代アイヌ文学とは何か 二節 現代アイヌ文学の潮流 三節 世界の先住民族文学との比較 四節 アイヌ文学の展望 あとがき 主な参考文献 近現代アイヌ文学史年表(1866〜2022) 文献索引 人名索引 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 須田茂(すだ・しげる) 1958年東京都生まれ。学習院大学法学部政治学科卒。民間企業に勤務する傍ら明治以来の近現代のアイヌ文学を研究。著書に『近現代アイヌ文学史論⸺アイヌ民族による日本語文学の軌跡〈近代編〉』、共著に『札幌地方同人雑誌作品選集 第1集』『北海道同人雑誌作品選集 第2集』がある。北海道文化財保護協会会員。神奈川県川崎市麻生区在住。
MORE -


シカバン 札幌〈映画〉生活史 1975-2024
¥2,420
“映画バカ”は世界中に棲息しておりますが、札幌にもこんな映画バカがおりました。 中3時代(1975年)から50年間、映画館や試写会場に足繁く通い、封切映画のベストテンをノートにつけ続けたある映画狂(シネマディクト)歯科医の映画まみれの半生記。読めばあの時代のあの映画を思い出し、誰かに「マイベスト映画(ワースト映画)」を語らずにはいられない! 門脇繁 著 2025年6月刊 四六判/並製/364頁 本体2200円+税〔税込2420円〕 ISBN 978-4-909281-70-8 C0074 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに [第一幕]歯科版 映画生活 歯科医に対するイメージ 二つのセリフ 女の顔に荒野を見た! 一九九五年という年 こんな夢を見た 頭の中のリンク 心を融かすもの 私家版・映画ベストテン 私のパラレルワールド 五〇半ばの初体験 言語によって世界は違って見える? 映画におけるクラシック音楽 師匠と呼べる存在 コロナ時代の映画ライフ タイムループと考えること 子どもが出てくる映画は「子どもの映画」じゃない 映画検定、 なんだそれ? 引き際の美学 [第二幕]私家版 ベスト映画 ワースト映画 一九七五年(昭和五〇年)の映画ベスト10 一九七六年(昭和五一年)の映画ベスト10 一九七七年(昭和五二年)の映画ベスト20 一九七八年(昭和五三年)の映画ベスト20 一九七九年(昭和五四年)の映画ベスト20 一九八〇年(昭和五五年)の映画ベスト20 一九八一年(昭和五六年)の映画ベスト20 一九八二年(昭和五七年)の映画ベスト20 一九八三年(昭和五八年)の映画ベスト20 一九八四年(昭和五九年)の映画ベスト20 一九八五年(昭和六〇年)の映画ベスト20 一九八六年(昭和六一年)の映画ベスト20 一九八七年(昭和六二年)の映画ベスト20 一九八八年(昭和六三年)の映画ベスト20 一九八九年(昭和六四年/平成元年)の映画ベスト20 一九九〇年(平成二年)の映画ベスト20 一九九一年(平成三年)の映画ベスト20 一九九二年(平成四年)の映画ベスト20 一九九三年(平成五年)の映画ベスト20 一九九四年(平成六年)の映画ベスト20 一九九五年(平成七年)の映画ベスト20 一九九六年(平成八年)の映画ベスト20 一九九七年(平成九年)の映画ベスト20 一九九八年(平成一〇年)の映画ベスト20 一九九九年(平成一一年)の映画ベスト20 二〇〇〇年(平成一二年)の映画ベスト20 二〇〇一年(平成一三年)の映画ベスト20 二〇〇二年(平成一四年)の映画ベスト20 二〇〇三年(平成一五年)の映画ベスト20 二〇〇四年(平成一六年)の映画ベスト20 二〇〇五年(平成一七年)の映画ベスト20 二〇〇六年(平成一八年)の映画ベスト20 二〇〇七年(平成一九年)の映画ベスト20 二〇〇八年(平成二〇年)の映画ベスト20 二〇〇九年(平成二一年)の映画ベスト20 二〇一〇年(平成二二年)の映画ベスト20 二〇一一年(平成二三年)の映画ベスト20 二〇一二年(平成二四年)の映画ベスト20 二〇一三年(平成二五年)の映画ベスト20 二〇一四年(平成二六年)の映画ベスト20 二〇一五年(平成二七年)の映画ベスト20 二〇一六年(平成二八年)の映画ベスト20 二〇一七年(平成二九年)の映画ベスト20 二〇一八年(平成三〇年)の映画ベスト20 二〇一九年(平成三一年/令和元年)の映画ベスト20 二〇二〇年(令和二年)の映画ベスト20 二〇二一年(令和三年)の映画ベスト20 二〇二二年(令和四年)の映画ベスト20 二〇二三年(令和五年)の映画ベスト20 二〇二四年(令和六年)の映画ベスト20 あとがき —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 門脇繁(かどわき・しげる) 1960年(昭和35年)、札幌市生まれ。歯科医師(口腔外科専門医、歯科顎関節症専門医)。 1979年、北海道札幌南高等学校卒業。1986年、北海道大学歯学部卒業後、同学部口腔外科学第二講座(現在の口腔顎顔面外科教室)入局。1993年、医療法人二期会歯科クリニック勤務。2007年、同法人理事。2014年4月〜2020年3月、同法人理事長。 キネマ旬報社「映画検定」二級。
MORE -

「銀河鉄道の夜」の謎を解く——〈彼ら〉はいったい何者なのか
¥1,980
国民的名作童話には《謎》がいっぱい。 賢治が遺した〈ことば〉を頼りにその謎解きに挑む《新感覚の文芸批評》! ●いじめられているジョバンニをカムパネルラはなぜ助けない? ●ジョバンニの父はなぜ監獄あに行った? ●沈没事故で死んだ姉弟はなぜ日本人なのか? ●「鳥捕り」が列車の乗り降り自由なのはなぜか? 「銀河鉄道の夜」を何度も読み返したくなる本。 三浦幸司 著 2022年3月刊 四六判/上製/184頁 本体1800円+税〔税込1980円〕 ISBN 978-4-909281-41-8 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 主な登場人物/物語のあらすじ 〔1〕ジョバンニはなぜ銀河鉄道に乗れたのか 第三次稿と第四次稿の違い ジョバンニと影との関わり ジョバンニの背負った苦難 父親が長期に不在(監獄にいるのかもしれない)とは カムパネルラの三度の沈黙 「ぼんやり」が意味するところ ジョバンニの上った「黒い丘」とは 「ケンタウル祭」はお盆――生と死がつながる行事 丘の上にある「天気輪の柱」とは何か ジョバンニはなぜ銀河鉄道に乗れたのか 〔2〕銀河鉄道は天空を走らない 銀河鉄道は空に昇らない 星と地上の一体化 空には星が残っていたのか 〔3〕「カトリック風の尼さん」とは何者か 銀河鉄道の様々な乗客たち 車内に現れた「尼さん」と「車室の中の旅人たち」 「尼さん」はジャンヌ・ダルクか 賢治の時代にジャンヌ・ダルクは聖人に 「ハルレヤ」を唱える人々 〔4〕「鳥を捕る人」の真実の姿 鳥獲りの容貌に注目しよう 鳥獲りは戦争の犠牲者 「ぼろぼろの外套」はアイデンティティー ほかにもある軍人のしるし 〔5〕「灯台守」とは何者か 「灯台守」は自立した労働者のこと 「灯台守」はなぜ「灯台守」なのか? 「灯台」=「時計台」という連想も 「灯台」は札幌の時計台だった? 〔6〕「姉弟」だけ日本人なのはなぜか 賢治の妹と弟がモデルの「姉弟」の登場 賢治はタイタニック号沈没事故を知っていたか 姉と弟だけなぜ日本人の名前なのか 「生き残った日本人」への非難 〔7〕「トウモロコシの種まきを語る人」とは何者か 声だけがする乗客 賢治が語った「アメリカンインデアンの式」 手塚治虫が捉えた「銀河鉄道の夜」の核心 〔8〕車窓から見える人たちについて 赤帽の信号手とはだれか 小さな小屋の前の子どもとは 空の工兵大隊の出現 シベリア出兵に向けた花巻での演習 双子の星の二つの話 「蝎の火」の物語 「ケンタウルの村」とは 赤い腕木を連ねて立つ二本の電信柱 〔9〕ジョバンニの友・カムパネルラのモデルとは 保阪説とトシ説 岩手山行の誓い 保阪嘉内の退学処分 「石炭袋」(そらの孔)と「きれいな野原」の意味 〔10〕カムパネルラとジョバンニにとっての「銀河鉄道」 カムパネルラの銀河鉄道 ジョバンニの銀河鉄道 ジョバンニの切符が意味するもの 「四つ折り」とは何を示すか 〔11〕銀河鉄道と路線についての不思議 銀河鉄道は軽便鉄道なのか 基本は銀河鉄道の位置関係の確定から 左岸を走る銀河鉄道とプリオシン海岸 〔12〕銀河鉄道の座席の位置 ボックスシートかロングシートか 乗客たちの座席の位置 右岸・左岸問題の解決 天の川銀河を見てみよう 終わりに——「銀河鉄道の夜」のテーマを考える 参考文献 あとがき —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 三浦幸司(みうら・こうじ) 1947年(昭和22年)、小樽市に生まれる。北大童話研究会、同人誌「原野の風」などに所属した。現在、日本児童文学者協会会員・評議員、北海道文学館理事、札幌市民芸術祭・市民文芸委員、子どもの本・九条の会会員、宮沢賢治学会イーハトーブセンター会員。札幌市在住。
MORE -

終わりなきタルコフスキー
¥2,860
ソ連の詩的映像作家アンドレイ・タルコフスキーが世を去って35年。しかし彼の作品への評価は高まることがあっても古びることは決してなく、映画館でも「タルコフスキー映画祭」が常に開催され、新しいファンを獲得し続けている。難解と言われるタルコフスキー映画全8作を詳細に解説すると共に全作品のフィルモグラフィーとタルコフスキー家の年譜も収録したタルコフスキー本の決定版。 忍澤勉 著 2022年1月刊 四六判/並製/440頁 本体2600円+税〔税込2860円〕 ISBN 978-4-909281-40-1 C0074 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに——永劫たる瞬間 第1章 物語の深淵——隠された意図 序 パステルナークの予言 〔1〕光と水の寓話——『ローラーとバイオリン』 〔2〕楽園への越境——『僕の村は戦場だった』 〔3〕無言の創造力——『アンドレイ・ルブリョフ』 〔4〕虚空の孤独——『惑星ソラリス』 〔5〕記憶の牢獄——『鏡』 〔6〕絶望の中の希望——『ストーカー』 〔7〕死に至る郷愁——『ノスタルジア』 〔8〕神なき者の祈り——『サクリファイス』 第2章 家族の投影——芸術的ポートレイトの深層 〔1〕追慕——『ローラーとバイオリン』 〔2〕憤怒——『僕の村は戦場だった』 〔3〕告白——『アンドレイ・ルブリョフ』 〔4〕帰順——『惑星ソラリス』 〔5〕解放——『鏡』 〔6〕離脱——『ストーカー』 〔7〕捕囚——『ノスタルジア』 〔8〕逃亡——『サクリファイス』 第3章 モチーフの躍動——物語を紡ぐ事物 〔1〕自然と動物 〔2〕身体と行為 〔3〕人工物・食物の属性 〔4〕超自然と信仰 第4章 核時代への視線——内包された予言 〔1〕この時代に携えるもの 〔2〕陸前高田の一本松とタルコフスキー 〔3〕初期の作品に描かれた「戦争」——第二次世界大戦下の核の風景 〔4〕『惑星ソラリス』——放射線の返礼 〔5〕『鏡』——汚染された煙と雨 〔6〕『ストーカー』——核イメージとしての放熱塔 〔7〕『ノスタルジア』——世界の終わりの風景 〔8〕『サクリファイス』——核戦争後の夜に 〔9〕黒澤明の『生きものの記録』との比較 〔10〕タルコフスキーの視線——私たちのバケツ 注 主な参考文献 年譜 あとがき——収斂と拡散 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 忍澤勉(おしざわ・つとむ) 1956年東京生まれ。編集プロダクション、広告制作会社、出版社勤務を経て、著述業。日本SF作家クラブ会員。「『惑星ソラリス』理解のために——『ソラリス』はどう伝わったのか」で第7回日本SF評論賞の選考委員特別賞を受賞。「ものみな憩える」で第2回創元SF短編賞の堀晃賞受賞、『原色の想像力2』(創元SF文庫)に収録。岡和田晃編『北の想像力』(寿郎社)では「佐々木譲論」を、同『現代北海道文学論』(藤田印刷エクセレントブックス)では「佐藤泰志論」を執筆。
MORE -

反ヘイト・反新自由主義の批評精神——いま読まれるべき〈文学〉とは何か
¥2,200
“批評”は停滞と閉塞を打ち破る。アイヌ民族・沖縄・原発などをめぐってSNSで欺瞞がはびこり、「極右」「オタク(萌え)」「スピリチュアル」な言説がもてはやされるなかで、気鋭の文芸批評家が放った渾身の“一矢”。 文学界・思想界からの反響・反発が必至の〈禁断〉の文芸評論集。 岡和田晃 著 2018年8月刊 四六判/並製/434頁 本体2000円+税〔税込2200円〕 ISBN 978-4-909281-12-8 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに Ⅰ ネオリベラリズムに抗する批評精神 ◉真空の開拓者——大江健三郎の「後期の仕事」 ◉「核時代の想像力」と子どもの「民話」——『はだしのゲン』への助太刀レポート ◉世界の革命家よ! 孤立せよ! ◉「歴史の偽造」への闘争——『日本人論争 大西巨人回想』 ◉文学に政治を持ち込む戦術の実践——陣野俊史『テロルの伝説 桐山襲烈伝』 ◉高橋和巳、自己破壊的インターフェイス ◉破滅の先に立つ批評——神山睦美『希望のエートス 3・11以後』 ◉「近代文学の終り」と樺山三英「セヴンティ」——3・11以後の〈不敬文学〉 ◉選び取り進むこと——山城むつみインタビュー Ⅱ ネオリベラリズムを超克する思弁的文学 ◉青木淳悟——ネオリベ時代の新しい小説 ◉「饒舌なスフィンクス」からの挑戦状——青木淳悟『匿名芸術家』 ◉『北の想像力』という巨大な〈弾〉 ◉『北の想像力』の試み——「仮説の文学」でネオリベに対峙 ◉『北の想像力』という「惑星思考」——山林に自由存せず、から始まる〈北海道文学〉史の再考 ◉「私」と〈怪物〉との距離——藤野可織の〈リアリズム〉 ◉日常の裏に潜む別世界——小山田浩子『穴』 ◉林美脉子という内宇宙 ◉「作者の死」、パンドラゲートのその先へ——林美脉子『タエ・恩寵の道行』栞文 ◉文学による「報道」——笙野頼子『さあ、文学で戦争を止めよう 猫キッチン荒神』 Ⅲ 北方文学の探求、アイヌ民族否定論との戦い ◉小熊秀雄を読む老作家・向井豊昭を読む ◉夷を微かに希うこと——向井豊昭と木村友祐 ◉アイヌ民族否定論の背景 ◉環太平洋的な「風景」を描いた民族誌——金子遊『辺境のフォークロア』 ◉私たちは『アイヌ民族否定論に抗する』をなぜ編んだか——岡和田晃×マーク・ウィンチェスター ◉北限で詠う詩人たち、「途絶えの空隙」とそこからの飛翔 ◉放射能が「降る降る」現実を前に——小坂洋右『大地の哲学 アイヌ民族の精神文化に学ぶ』 ◉中央の暴力を掻き回す辺境の言葉——向井豊昭『怪道をゆく』 ◉ノッカマップを辿り直して ◉「がんばれニッポンっ!」という空白を埋める——木村友祐『イサの氾濫』 ◉生きられる隙間を探せ——木村友祐『野良ビトたちの燃え上がる肖像』 ◉歴史修正主義に抗する先住民族の「生存の歴史」——津島佑子『ジャッカ・ドフニ』 ◉津島佑子と「アイヌ文学」——pre-translationの否定とファシズムへの抵抗 ◉歴史修正主義と〈マイノリティ憑依〉をともに打破する言葉はどこか——教育者にして作家・向井豊昭の調査と思索、その原点 ◉〈アイヌ〉をめぐる状況とヘイトスピーチ——向井豊昭「脱殻」から見えた「伏字的死角」 ◉「文化振興」に矮小化される「アイヌ政策」を批判、表象と政治のねじれた関係を解きほぐす——計良光範『ごまめの歯ぎしり』 ◉マイノリティ相互の関係史を資料と証言で掘り下げる——石純姫『朝鮮人とアイヌ民族の歴史的つながり』 ◉江原光太と〈詩人のデモ行進〉——『北海道=ヴェトナム詩集』再考 ◉江原光太と〈詩人的身体〉——郡山弘史、米山将治、砂澤ビッキ、戸塚美波子らを受け止めた器 ◉断念の感覚の漂着点——中原清一郎『人の昏れ方』 ◉異議を申し立てる文学——木村友祐『幸福な水夫』 Ⅳ 沖縄、そして世界の再地図化へ ◉沖縄の英文学者・米須興文の「二つの異なった視点」——主に『ベン・ブルベンの丘をめざして』収録文から考える ◉移動と語りの重ね書きによる世界の再地図化——宮内勝典『永遠の道は曲りくねる』 あとがき —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 岡和田晃(おかわだ・あきら) 1981年、北海道上富良野町生まれ。早稲田大学第一文学部卒。筑波大学大学院人文社会科学研究科で修士号を取得。文芸評論家、ゲームデザイナー、東海大学文芸創作学科非常勤講師。「「世界内戦」とわずかな希望——伊藤計劃『虐殺器官』へ向き合うために」で第五回日本SF評論賞優秀賞受賞(2010年度)。2014年、『北の想像力——《北海道文学》と《北海道SF》をめぐる思索の旅』(編集、寿郎社)で第35回日本SF大賞最終候補。2016年、『破滅(カタストロフィー)の先に立つ——ポストコロニアル現代/北方文学論』で第50回北海道新聞文学賞創作・評論部門佳作。2015年の『アイヌ民族否定論に抗する』(共編著、河出書房新社)は広く話題となり、関連して、反ヘイトの評論・公演活動を行なう。 その他の著作に『アゲインスト・ジェノサイド』(新紀元社)、『「世界内戦」とわずかな希望 伊藤計劃・SF・現代文学』(アトリエサード)、『向井豊昭傑作集 飛ぶくしゃみ』(編著、未來社)、『向井豊昭の闘争 異種混淆性(ハイブリディティ)の世界文学』(未來社)、『世界にあけられた弾痕と、黄昏の原郷——SF・幻想文学・ゲーム論集』(アトリエサード)、『石牟礼道子——さようなら、不知火海の言魂』(共著、河出書房新社)など。『エクリプス・フェイズ』(筆頭訳、新紀元社)ほか翻訳書も多数。 日本文藝家協会、日本SF作家クラブ、日本近代文学会、それぞれ会員。
MORE -

近現代アイヌ文学史論⸺アイヌ民族による日本語文学の軌跡〈近代編〉
¥3,190
アイヌ民族によって書かれた文学(小説・評論・詩歌)のすべてを論じた日本初のアイヌ文学通史——その上巻「近代編」がついに完成。 刺激的な内容と五〇〇ページを越えるボリュームで日本文壇と学会、読書界に波紋を呼ぶこと必至の大著! 須田茂 著 2018年4月刊 四六判/並製/528頁 本体2900円+税〔税込3190円〕 ISBN 978-4-909281-02-9 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 序章 一節 「近現代」という時代区分について 二節 近現代のアイヌ民族における「文学」 三節 「アイヌ民族」の範囲 第1章 異言語(日本語)の強制と同化教育 一節 キリスト教によるアイヌ教育 二節 日本政府のアイヌ教育 三節 独立系のアイヌ教育 四節 金成太郎の位置 第2章 樺太からの発信〈その1〉——山辺安之助『あいぬ物語』 一節 山辺安之助の『あいぬ物語』の梗概 二節 『あいぬ物語』の出版経緯 三節 『あいぬ物語』の編集過程 四節 『あいぬ物語』の文学的評価 第3章 樺太からの発信〈その2〉——アイヌの民俗誌 一節 『極北の別天地』——バフンケ、アトイサランデ、シベケンニシの声 二節 千徳太郎治の『樺太アイヌ叢話』 三節 『樺太アイヌ叢話』について 四節 『樺太アイヌ叢話』の謎 第4章 武隈徳三郎の『アイヌ物語』とその周辺 一節 武隈徳三郎の『アイヌ物語』の出版経緯 二節 『アイヌ物語』の内容と意義 三節 知られざる武隈の生涯の解明 第5章 知里幸惠の『アイヌ神謡集』——原風景の創出 一節 知里幸惠の略歴 二節 アイヌ文学史における業績 三節 知里幸惠の文学の鉱脈 四節 『アイヌ神謡集』の波紋 五節 『アイヌ神謡集』の普遍性 第6章 詩歌人たちの登場——内なる越境の始まり 一節 違星北斗の文学と思想 二節 バチェラー八重子の献身 三節 森竹竹市の詩歌と訴え 第7章 近代後期の言論者たち 一節 貝澤藤蔵と『アイヌの叫び』(一九三一年) 二節 貫塩喜蔵(法枕)と『アイヌの同化と先蹤』(一九三四年) 三節 『蝦夷の光』を舞台とした言論(一九三〇〜三三年) 四節 辺泥和郎と『ウタリ乃光リ』(一九三二〜三四年) 五節 川村才登と「アイヌの手記」(一九三四年) 第8章 近代後期のキリスト教系アイヌ文学の系譜——ジョン・バチェラーの弟子たち 一節 『ウタリグス』(一九二一〜二五年?) 二節 『ウタリ之友』 三節 片平富次郎(一九〇〇〜五九年) 四節 向井山雄(一八九〇〜一九六一年) 五節 上西与一(?〜一九四四年?) 六節 知里高央(一九〇七〜六五年) 七節 山内精二(一九一一〜八五年) 八節 江賀寅三(一八九四〜一九六八年) 第9章 内なる越境文学としての近代アイヌ文学 一節 越境文学とは何か 二節 「内なる越境」とその特徴 三節 近代日本とアイヌ民族の「内なる越境」 四節 近代アイヌ文学のテーマとして「同化」と「同化政策」 五節 近代アイヌ文学の声、再び 六節 近代アイヌ文学の特徴と意義——結論として あとがき 主な参考文献 人名索引 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 須田茂(すだ・しげる) 1958年東京都生まれ。学習院大学法学部政治学科卒。民間企業に勤務する傍ら明治以来の近現代のアイヌ文学を研究し、その成果を「近現代アイヌ文学史稿(一)~(八)」として札幌の同人誌『コブタン』に発表。現在同誌に「現代編」を連載している。北海道文化財保護協会会員。神奈川県川崎市在住。 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【正誤表】 『近現代アイヌ文学史論〈近代編〉』の文中に誤りがありました。お詫びして下記の通り訂正いたします。(著者 須田茂) ●25頁7~11行目 誤 北海道アイヌ協会は、「北海道ウタリ協会」であった一九八〇年から自らアイヌ史編纂に着手し、北海道ウタリ協会アイヌ史編集委員会が『アイヌ史資料集』の発行を逐次開始した。現在までに第一期全八巻〔一九八〇年〕、第二期全七巻〔一九八四年〕が刊行されている。これは主に研究資料としての価値を認められた一次資料を収集・編纂したものである。しかしながらこれはあくまで歴史的資料の収録が中心で、アイヌ民族独自の視点に立った歴史観が示されたものではなかった。また一部の差別的視点が問題となった〔註3〕。」 正 北海道アイヌ協会は、「北海道ウタリ協会」であった一九八二年から自らアイヌ史編纂に着手していたが、紆余曲折を経て、北海道ウタリ協会アイヌ史編集委員会が『アイヌ史 資料編』〔第1巻~第4巻〕及び『北海道アイヌ協会・ウタリ協会 活動史編』〔第5巻〕の発行を逐次開始した。これは主に研究・参考資料としての価値を認められた諸資料・所蔵目録等を収集・編纂したものである。しかしながらこれはあくまで歴史的資料の収録が中心で、アイヌ民族独自の視点に立った歴史観が示されたものではなかった。(*1) ●34頁6~10行目 〔註3〕は削除します。 ●48頁4行目 誤 開校した 正 閉校した ●53頁7行目〔 〕内 誤 野村義一『野村義一と北海道ウタリ協会』 正 竹内渉『野村義一と北海道ウタリ協会』 ●88頁7行目(小見出し含む) 誤 説術者 正 説述者 ●89頁13~14行目(小見出し含む) 誤 三人の「説述者」はいずれも樺太から北海道への強制移住者で、北海道での不漁続きにより樺太に帰還したという人たちである。 正 全文削除します。(*2) ●89頁17行目~90頁1行目 誤 もうひとりの「説述者」であるシベケンニシについては山辺安之助の一歳年少であり、対雁で日本語を学んだ可能性がある。 正 全文削除します。(*2) ●149頁2行目 誤 知里高央 正 知里高吉 ●164頁7行目 誤 たち 正 だち ●169頁5行目 誤 津島祐子 正 津島佑子 ●241頁最終行 誤 常任幹事 正 常任監事 ●346頁1行目 誤 副会長 正 副理事長 ●364頁1~2行目 誤 北海道アイヌ協会の理事に就任 正 北海道アイヌ協会の監事、その後理事に就任 ●506頁18行目 誤 野村義一 正 竹内渉 ●521頁(人名索引) 誤 チェフサンマ 正 チュフサンマ 誤 知里高吉 正 149頁を追記 誤 知里高央 正 149頁を削除 誤 津島祐子 正 津島佑子 (*1)北海道ウタリ協会(当時)は河野本道著『アイヌ史資料集』の刊行には関与しておりません。ご指摘ならびにご教示いただきました竹内渉様に感謝いたします。 (*2)削除理由:三人の「説術(述)者」が強制移住者であるとの記述に誤りがあるため。ご指摘いただきましたエンチウ(樺太アイヌ)協会様に感謝いたします。
MORE -

ごまめの歯ぎしり
¥2,860
北海道から世界に向けて〈アイヌ文化〉や〈先住民の権利〉について発言し続けてきた著者の20年わたる反骨のコラム集。 計良光範 著 2016年3月刊 四六判/上製/464頁 本体2600円+税〔税込2860円〕 ISBN 978ー4ー902269ー86ー4 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 〈はじめに〉と解題 一 これがアイヌ刺繍か——大滝村ドライブインの展示 二 ついに「焚書」か——長見義三の小説『アイヌの学校』 三 最新、最悪の博物館——旭川博物館 四 「熊牧場」へ行った——登別クマ牧場 五 部落差別は北海道にも現存する——西本願寺札幌別院差別落書事件 六 平和な国の恐怖劇——オウム真理教と阪神大震災 七 いま「市民」は——映画『ハーヴェイ・ミルク』 八 演劇評論家ではないけれど——学校祭のための脚本と某専門劇団の脚本 九 再び部落差別の存在について——差別落書きは続いた 一〇 船戸与一『蝦夷地別件』のこと ほか —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 計良光範(けいら・みつのり) 1944年、北海道蘭越町生まれ。《ヤイユーカラの森》運営委員長、北海道教育大学非常勤講師を務めた。 著書に『アイヌ文化の実践——《ヤイユーカラの森》の二〇年(上・下)』『アイヌ社会と外来宗教——降りてきた神々の諸相』(以上、寿郎社)、『北の彩時記』(コモンズ)、『ハンドブック 国際化のなかの人権問題〔第4版〕』『新版 近代化の中のアイヌ差別の構造』『アイヌの世界』(以上、明石書店)、『講座 差別の社会学 第4巻 共生の方へ』(弘文堂)がある。 2015年3月、がんのため逝去。享年71。
MORE -

〈物語る脳〉の世界——ドゥルーズ/ガタリのスキゾ分析から荒巻義雄を読む
¥2,750
日本SF界の巨匠・荒巻義雄の代表作を、精神科医・批評家である著者が、現代フランス思想の革命児ドゥルーズ/ガタリの理論をもちいて表裏から徹底的に読み解いた文芸評論のみならず現代思想にも一石を投じる快著。 藤元登四郎 著 2015年10月刊 四六判/仮フランス装/352頁+口絵8頁 本体2500円+税〔税込2750円〕 ISBN 978ー4ー902269ー80ー2 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第1部 荒巻義雄のSF機械のスキゾ分析 第1章 荒巻義雄とドゥルーズ/ガタリ 第2章 スキゾ分析の手順 第2部 荒巻作品のスキゾ分析 [短編] 第1章 シュルレアリスムの絵画との境界消滅 第2章 物語の世界との境界消滅 第3章 主体はその時点で生成される 第4章 世界の始まりと終わり [長編] 第1章 『時の葦舟 SF連作集』 第2章 『白き日旅立てば不死』 第3章 『神聖代』 第4章 『カストロバルバ——エッシャー宇宙の探偵局』 おわりに 解説 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 藤元登四郎(ふじもと・としろう) 1941年(昭和16年)宮崎県都城市生まれ。東京大学医学部卒。医学博士。精神科医・SF評論家。日本SF作家クラブ会員。「『高い城の男』——ウクロニーと「易教」」で第6回日本SF評論賞選考委員特別賞を受賞。 著書に『シュルレアリスト精神分析——ボッシュ+ダリ+マグリット+エッシャー+初期荒巻義雄/論』(中央公論事業出版)、訳書に『フランス流SF入門』(幻冬舎ルネッサンス)、共著に『北の想像力——《北海道文学》と《北海道SF》をめぐる思索の旅』(寿郎社)がある。
MORE -

北の想像力——《北海道文学》と《北海道SF》をめぐる思索の旅
¥8,250
“文芸評論の力”を信じる20人の批評家たちが、《北海道文学》と《北海道SF》をSFとして読み直し、日本近代文学の限界をもあぶり出しながら新たな文学の可能性を見出した、日本文学史上画期をなす評論大全。 岡和田晃 編 2014年5月刊 A5判/上製/708頁 本体7500円+税〔税込8250円〕 ISBN 978ー4ー902269ー70ー3 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 序論 「北の想像力」の可能性 第1部 「北の想像力」という空間 第2部 「北の想像力」とSF史 第3部 「北の想像力」と科学 第4部 「北の想像力」と幻想 第5部 「北の想像力」とリアリズム 第6部 「北の想像力」と海外/メディア 第7部 「北の想像力」を俯瞰する —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【編者略歴】 岡和田晃(おかわだ・あきら) 1981年北海道上富良野町生まれ。早稲田大学第一文学部文芸専修卒業。筑波大学大学院人文社会科学研究科文芸・言語専攻一貫制博士課程在学中。批評家、ライター。日本SF作家クラブ、speculativejapan会員。活動の核に文学を据え、境界解体的な活動を旨とする。
MORE